たまろぐ
テツ的あれこれ妄想牧場。(※路線≒会社の擬人化前提注意です)
最近は管理人の備忘録と化してます。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
あいかわらず、線画の取り込みがひどいわけですが。



前髪がオソロイぽくなったのは、たまたまです。
たまたまなんですが、ある意味ガッツポーズです。ウェ~イ。
(バリエーションがないともいう)
どうしても、これ以上小っちゃい幼児が描けないなぁ・・・
着工前なんだから、もっと小っちゃくてもいいはずなんですが。
(工事の進捗に従って背が伸びていくイメージ、免許線が完了すれば成人、的な?)
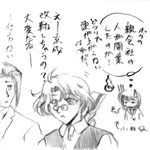
鬼怒電おいしゅうございました(ー人ー)
======================================
拍手ありがとうございます!
ここ一ヶ月ほど冗談でなく絵を描いていないので、気ばかり焦ります。
どうにも右肩が痛くて、7月(横浜いった日)にレントゲン撮ったんですが骨はなんともないから、うち(整形外科)じゃないね、シップでも貼っとけば、といわれ、抗生物質と消炎剤にロキソニンもらったんですが、すげー納得いかぬ・・・。ロキソニンなんて普段から飲んどるし、実際全然効いてないし・・・。orz
温湿布貼ったらますます酷くなったんで、どーしたもんかなーと、思ってたんですが、今朝おもいつきで去年術後に貰った外用鎮痛消炎剤のインデバンクリーム塗ったら、なんか、治まってきたみたいな。う~ん、原因は結局よくわからないです。
残暑がきびしいですね。自分もここ数日、体調がグロッキーです。
そのわりに食欲はバリバリなんで、夏に痩せるなんて都市伝説だと思っています残念です。
週末に出掛けるということが、とてもできそうもないかんじで、この夏はイベント全部逃してるんですが、冬は・・・冬は行きたい!でも仕事で厳しいかな。
それよりも、汗で用紙が腕に張り付いてくるのが、目下の大問題です。
はやく涼しくな~れ~
前髪がオソロイぽくなったのは、たまたまです。
たまたまなんですが、ある意味ガッツポーズです。ウェ~イ。
(バリエーションがないともいう)
どうしても、これ以上小っちゃい幼児が描けないなぁ・・・
着工前なんだから、もっと小っちゃくてもいいはずなんですが。
(工事の進捗に従って背が伸びていくイメージ、免許線が完了すれば成人、的な?)
鬼怒電おいしゅうございました(ー人ー)
======================================
拍手ありがとうございます!
ここ一ヶ月ほど冗談でなく絵を描いていないので、気ばかり焦ります。
どうにも右肩が痛くて、7月(横浜いった日)にレントゲン撮ったんですが骨はなんともないから、うち(整形外科)じゃないね、シップでも貼っとけば、といわれ、抗生物質と消炎剤にロキソニンもらったんですが、すげー納得いかぬ・・・。ロキソニンなんて普段から飲んどるし、実際全然効いてないし・・・。orz
温湿布貼ったらますます酷くなったんで、どーしたもんかなーと、思ってたんですが、今朝おもいつきで去年術後に貰った外用鎮痛消炎剤のインデバンクリーム塗ったら、なんか、治まってきたみたいな。う~ん、原因は結局よくわからないです。
残暑がきびしいですね。自分もここ数日、体調がグロッキーです。
そのわりに食欲はバリバリなんで、夏に痩せるなんて都市伝説だと思っています残念です。
週末に出掛けるということが、とてもできそうもないかんじで、この夏はイベント全部逃してるんですが、冬は・・・冬は行きたい!でも仕事で厳しいかな。
それよりも、汗で用紙が腕に張り付いてくるのが、目下の大問題です。
はやく涼しくな~れ~
PR
明治43年7月27日の東京朝日新聞の広告に鬼怒川水力電気株式会社の創立委員と発起人の一覧が載ってたんですが、京王の初期重役陣とメンバーが完全に一致してた。
ここまで露骨だと・・・なんだかな・・・。(=口=;;)
明治43年9月の京王電気軌道の創立総会で決定した面子が↓
取締役社長 川田 鷹
専務取締役 利光丈平
取締役 豊原基臣、太田信光、井倉和欽、濱 太郎
監査役 吉田幸作、岡 烈
緑の●がそうです。青いほうは京成の重役で名前があった人たち。
明治42年6月30日の創立総会の京成の役員は以下。
専務取締役 本多貞次郎
取締役 桂二郎、関博直、土居貞次、板橋 信
監査役 渡辺勘十郎、皆川文明、
相談役 松平正直
明治44年3月17日の約款改正での新規重役(利光議長の指名による)は以下
取締役 井上敬次郎、本多貞治郎、森久保善太郎、北岡鶴松、
土居貞次、利光鶴松、上原鹿造、安東敏之、木村省吾、梅原亀七
監査役 平沼専蔵、乙訓寛吉、藤江章夫、安藤保太郎
で、会長、専務は後日、井上敬次郎、本多貞治郎両氏が互選されます。
「京成電鉄五十五年史」によると、京成の胎動期、計画線の路線部分が3派競願になり、
第一:本多貞次郎、利光鶴松、野中万助、井上敬次郎の東京市街鉄道派
第二:郷誠之助男爵、飯村丈三郎、川崎八右衛門、本多弘の川崎財閥派
第三:松平正直男爵、内藤善雄、鈴木峯吉ら貴衆両議員約200名による一派
の泥沼の様相となったものの、本多氏の献身的な工作と、内務大臣原敬信任の
小山田信蔵代議士の仲介で合同を条件の特許内意があり、と
なりたちが東京市街鉄道のときと同様の内容だったといいます。
それゆえ京成はかならずしも利光一派が全部、というわけでもなかったみたいですが、
それでも京成開業まで会社を引っぱっていったのは、本多さんの努力あってだからなぁ。
鬼怒電の大口受電先の確保として小田急を、という話は聞きますが、
時代的には京成や京王もおもいっきり、そうだったんじゃないかなーと。
これは広告から四日後の続報。
「●鬼怒川水電許可 ▽市内配電も許可」明治四十三年七月三十一日 朝日新聞
従来逓信省に於ては無用なる競争と危険を防止せんが為に東京鉄道以外には
東京市内に於ける配電を許可せざることに内定せり
其結果桂川水電を始め各種の水電は早くより市内配電を申請せるも其都度之を却下せり
然るに鬼怒川水電は愈之が創立も確実となれるのみか太田黒派と合同して
企業一層有望となれるを以て大に逓信省の信用する所となり本月二十七日附けの申請に
対し意外にも昨三十日附けを以て東京市の外府下荏原、豊多摩、豊島、南足立、南葛飾
の郡部への配電を許可したり
命令書に依れば配電許可の期間は二十五ヶ年にして六ヶ月以内に会社を組織して
三ヶ年以内に営業を開始し郡部は架空線式の配電を許可するも市内にありては最初より
地下線式を採るべき義務を負ひ配電の分量には一邸宅又は構内に付き百馬力以下の送電
を禁止して東灯及び東鉄との競争を或程度まで予防したり尤も動力を使用する工場への
配電分量には何等の制限なきものの如し
配電許可の範囲も、東京市内だけでなく府下の豊多摩や南葛飾など市内外縁まであったようです。
実際、京成は大正2年5月15日鬼怒川水力と電力需給契約を締結していますし。
太田黒派と合同というのは、これかな。
「●両鬼怒水電合同」明治四十三年七月十七日 朝日新聞
鬼怒川流域中の中の島より中岩橋に至る区域は太田黒一派が水利権を掌握し居りしが
鬼怒川水電は之と合同せんとする希望を抱き従来秘密に協議進行中なりしが
愈十六日に至り鬼怒水電の利光鶴松氏が太田黒重五郎、白杉政愛、久野昌一の三氏と
会見の結果円満に合同談は成立し契約を締結するに至りたり
其の合同條件は太田黒派にて水利権一切を鬼怒電に移転する代りに之が調査設計其他
の費用として三万円を鬼怒水電に於て支出弁償し且権利株五十株を分与する事、
太田黒派の発起人は全員を挙げて鬼怒川水電の発起人に加名し其内久野、白杉、太田黒
の三氏は創立委員として参加するに決せり
太田黒一派といのは、発起人広告の紫●のひとたちです。無事合流したんだね。
さらにこれに日英水電が加わるかどうか、という記事が以下。
「●両水電合同難」明治四十三年七月二十三日 朝日新聞
太田黒重五郎久野昌一両氏は今回の鬼怒両水電合併後更に一歩進めて
鬼怒日英両水電の合同を企てたるも日英水電の主力は今や邦人の手を離れて
英国なる神戸シンジケートの掌中にあり
実に英人側に於て先にハウエル技師等に三万の俸給を払ひ遙々日本に渡航せしめたるを始め
スペヤリング商会のストラッセー氏渡米に至るまで日英水電の為に投ぜられたる資金は
英国側にのみにて既に五十万円に達し今や気息奄々たるの窮状にありとは云へ
相当の補償條件を与へて英人を満足せしめざる限り無条件の下に鬼怒水電と合同するを悦ばず
現に英京なる神戸シンジケート宛て合同賛否の照電を発せるに其回答は遅々として明快なる応答を与へず
加ふるに本邦株主側は既に申込証拠金の返戻を受けて
日英水電と関係を絶ちたる今日とて合同の成行を冷視するの傾きあり
一説には鬼怒電の進行上、日英水電側と和衷協同の態度に出でざる限り
三菱、三井、十五各銀行の系統は井、松両侯の手前を憚り鬼怒電に賛助を与へざるが為め
頻りに合同を声言して其歓心を買はんとするものなりと観察するものなり
利光さんの手記に、
「明治四十三年頃は、日露戦役後、成金時代の反動期にして、成金時代に各種の事業を
発起し財界の恐慌に襲はれて新事業は皆悉く悲惨なる逆境に陥り、未だ全く恐怖心の
消散せざる時代なれば、一般に新事業を起す事は殆んど絶望と称すべき形勢なり。
特に水力電気に対する国民一般の智識経験は頗る幼稚にして、
資産家は容易に之に投資するを肯ぜざるなり。
現に日英水力の如きは、園田孝吉男(爵)氏を委員長とし、三井家の朝吹英二(常吉
氏の厳父)早川千吉郎氏等之に加はり、其他三菱系は勿論我邦一流の富豪を網羅したる
団体にして、国家の元老井上(馨)松方(正義)の両侯を後援し、桂首相、小村外相は
英国資本家を之に結び付くるの役目を承はりて斡旋の労を取り、其委員会は時々永田町
の首相官邸に開けり。而して日英水力は東京鉄道に電力供給の契約を締結し居りたれば、
会社を創立するは実に容易の筈なり。然るに其創立容易ならず、東鉄会社に対する電力
供給契約を再度迄延期したるも遂に契約所定の期日迄に会社を創立すること能はずして
供給契約は解除となれり。此一例を以て之れをとするも、当時水力電気事業を起すの
頗る困難なるを了解するに充分ならん。」
とあり、日英水力とは、英国資本と提携して、大財閥と元老がバックに付いたかなり大規模な水電計画だったことがうかがえます。
記事中の「井、松両侯」というのは、井上馨と松方正義両氏のことだったんですね。
しかもまずは「日英水力は東京鉄道に電力供給の契約を締結し」ていたというのも、この大御所メンツならさもありなんです。
しかし、東京水力電気を前身とする鬼怒川水力創立準備組合が、エー・ウェンデル・ジャクソン氏の英国外資導入で躓いたのと同様、こちらもなかなか話が進捗しなかったようです。
しかし、利光氏は頓挫しかかった鬼怒電の事業に憤然と起ち上がって、内資でもって計画を継承し、その資金集めのために東奔西走して、事業を成し遂げます。
「外資導入計画が不成功に終わったので、鬼怒川水力電気株式会社準備組合の常任委員田 健治郎氏は、到底会社設立の見込み立たず、と断念して手をひくこととなり、創立準備組合も明治四十三年五月三十一日で解消してしまった。
ここに新進気鋭の幾人かは、徒らに他力本願的な外資導入に依存して、折角の計画を
不成功に終わらせた結果に憤激して、新たに内資によってあくまで素志を貫徹しようと蹶起した。
利光鶴松氏は、その主唱者であった。」(小田急二十五年史)
「●水電界の外交」明治四十三年四月一日 朝日新聞
鬼怒川水電は既報の如くジャクソン氏と絶縁し内資起業に決定し居れるも
四月同水電組合の定時総会を俟って発表すべき予定の下に満を持して放たず
利光鶴松氏の如き殆どジ氏契約を忘れたるが如く京阪地方より名古屋方面に
閑遊を試みジ氏の相手とならず是に於てジャクソン氏の懊悩は今や極点に達し
屡々倫敦に飛電を発して何事かハナウ氏と打合する模様なりしが最近に於て
先に提唱せる條件中(一)英国法の下に会社を組織すると(二)存続期間
二十年を五十年に改むるとの二ヶ条は之を取消し単に対東鉄契約期間十年を
二十年とする條件のみを保留して新に協議を進めたき意向を漏らせるも
鬼怒川幹部は未だ耳を傾くに至らず
「●鬼怒川水電関西発起人」明治四十三年七月六日 朝日新聞
鬼怒川水電の発起人は東西を通じて既に百余名に達したるが関西実業家より
発起希望を申込み会社側に於いても年来の関係上今更関西有力者を度外視する
能はざるの事情あり利光鶴松小林清一郎の両氏は去月末右発起者引続纏めの為
下阪し関係者を一堂に会して他日の誤解なき様実測図に就きて詳細なる説明を
与へ帰京せられたるが主なる発起者及賛成者左の如し
(大阪)田中市兵衛、土居通夫、田邊貞吉、浮田圭造、本山彦一、岩下清周、
広岡恵三、片岡直温、中橋徳五郎、島村久、田艇吉、梅原亀七、野村徳七、
宅徳平諸氏の外三十六名
(京都)田中源太郎、木村省吾、谷村一太郎、曾野作太郎、古河為三郎、
藤井善介、津田栄太郎、稲垣敬次郎、藤原忠一郎
(神戸)村野山人、金子直吉
金子さんでてきた!\(^0^)/
この結果、鬼怒電の発起人には東西の資本家が勢揃いするすごい人数になったのですね。
金子直吉さんは、賛成人ですが、岡烈さんは、発起人の一人として名を連ねています。
千代田瓦斯の創立は、鬼怒川水力の発起と時期が並行していて、どっちが先とか後とかは分からないんですが、この辺を通じて神戸鈴木商店の関東進出がすすんでいったのかなぁ・・・と。
ちなみに、京成の社史p145にも
「こうして会社は創立されましたが、このままでは第2回の払い込みも不安なばかりでなく、今後の社運営業上からも急速に経営内容充実を図る必要があるので本多専務は先輩知人を煩わし、更に整理委員を設けて株主強化に着手、このため安樂兼道を委員長とし、そのほか多数の委員を委嘱しました。そして大阪方面では野村徳七・松本重太郎・梅原亀七・竹原荘次郎・柴山鷲雄・京都では木村省吾、名古屋では奥田正香・横浜では平沼専蔵など多くの援助賛成者を獲得・更に賀田金三郎・太田黒重五郎・大塚常治郎・岡烈・小池国三・荒井泰治・藤江章夫・横田千之助など東京周辺の協力者も得て懇請した結果、野村徳七、奥田正香、木村省吾のほか賀田・大塚・岡・小池・荒井・太田黒・平沼・岩下などが引き受け、肩替わりに成功しました。この努力によって第2回の払い込みはもちろん会社として積極的運営の目標が確立しましたので、測量・土地買取に取りかかることになったのです。」
と岡烈さん、他、鬼怒電で一緒になった人たちの名前が随分散見されます。
ちなみに、広告の赤●は、東京電車鉄道時代からの東鉄の重役です。
京成の青●の人でも、井上敬次郎さんは東鉄常務だし、安藤保太郎さんは東鉄の電灯部の主任だったみたいで、「これもう出来レースじゃねえか (=口´=;」って思うんですが、事はそう簡単な話じゃなかったみたいで、
ふたたび利光さんの手記より
「東京鉄道と電力供給契約を締結せしは、会社創立の前年即ち明治四十二年にして、
準備組合時代なり。其契約に於ては最高弐万馬力を供給するの約束なり。後会社創立
の翌年、即ち明治四十四年五月に至り追加契約を為し結局五万馬力迄を供給するの
約束となれり。
初め東鉄は、日英水力と弐万馬力買収の契約を結びたるに、日英水力は会社を成立
すること能はず、再度迄契約の延期をなしたるも遂に会社を成立し能はざるに依り、
東鉄は日英水力の契約は之れを破棄し、他に電源を求むるに至れり。
鬼怒川動力会社準備組合は是に於て、日英水力に代りて東鉄と電力供給契約を結び
たるなり。其電力供給契約を結ぶに当りて非常なる競争起り、予は此際より既に幾多
の苦労せり。其の時東鉄に電力を売込まんとして競争を試みたるは、安田(善次郎)
雨宮(敬次郎)小野(金六)氏等の桂川水力、浅野総一郎氏の吾妻川水力、大岡育造、
川原茂輔氏等の大利根水力、東京電灯会社、前に一旦破約されたる日英水力並に
鬼怒川動力会社準備組合等なり。
競争劇甚の結果、東鉄は其取捨に迷ひ、井上敬次郎、児玉隼槌、吉村恵吉氏等は、
実地を踏査し、工費低廉にして速成の見込充分なるものを撰び之れと契約を結ぶを、
東鉄の利益と決し、鬼怒川水力は其条件を具備する水力と認められて月桂冠を戴けり。
再び云ふ予が其間の苦心は容易ならざるものありたり。」
日英水電がダメになって、東鉄が電源をほかにもとめ、それを狙って奪い合いがおこり、
鬼怒電に決まったのが明治42年ということなので、利光さんが先頭に立って事を起こす前ですね。
むしろ、そこから両社が接近していったと考えるべきか・・・。ふむ~ん。
京王に関しては、初期重役陣がしくって、川田鷹さんが森村さんに相談をし、森村さんが和田さんにはかって、和田さんがこれを引き受けたため、途中から富士瓦斯紡績圏内にはいっちゃうんですよねぇ。
富士紡の和田さんは玉電の津田興二専務と知り合いで、富士紡の余剰電力を活かすために電力需給契約を締結、駒沢に変電所を設け「東京幹線」を確立させる事によって、富士紡は供給区域をゲットするんですが、それが明治44年~大正2年10月。
京王は大正4年、玉電から受電を開始するようになります。
会社の、調布駅を利用している人が、昨日の夜の付け替え完了したばかりの駅を見たよというので、
「どんなかんじだった?ホームドア、あったでしょ、」と聞いたら、「あるけど、開きっぱなしだった」という返答で
「・・・・・・・・え?」
気になったので、ちょっと見てきました。昼休み使って。


マジだった。
電車が行っても、開きっぱなし。電車がきても開きっぱなし。相模原線のもおなじく。
これじゃあ、単に、とびとびで板が生えただけじゃ?
(都営車の表示が回送。これは調布止まりで、このあと引き込み線にでも待避するのかな~)

・・・しかも、なんか都心の地下で見るホームドアより、間が広いような・・・。
多少のオーバーランも大丈夫b って事なんでしょうか・・・。
運転士さんが馴れるまでは本格起動しないとか?(笑)よくわからんですが、まだまだ未完成のようです。



そして、壁の絵がむしろ怖いよ、ケイオウさん・・・。
ピンクは新宿の(京王関係の)景色かな。なにげに都庁も入れてるのは、都営への配慮?
上り線のホームから、エスカレーターをあがると下り線のホームにでました。
そこでさっそく、出口と間違えて下りのエスカレーターに乗ろうとし、止められるお年寄りの一団。
こりゃあ、しばらく混乱がおきそうだわ。
警備保障かなにかの人が、ホームにも改札にもすっごい、いっぱいいました。

中央改札口。これとは反対側に東口改札口もあるのだけど、私も一瞬混乱しました。
どっちにでても、北側南側に出られるので、別に迷うことはないんですよね。はへー

外へ出ました。中央改札からの階段は、橋上駅のときのと同じ、架設の階段でした。
途中の通路に工事中の様子や、京王線の昔の駅の写真がすこし展示されていましたが、
それがはっつけてある壁も、柔らかくて仮素材っぽい・・・。今後どうなるんでしょう、あの動線。



京王線の線路が、はやくもバッツリ切断されてて、横断歩道にされてるのに驚きました。
ここから、無人となった駅の地上ホームが見られます。
なんか、もう資材置き場と化してましたが。



相模原線の分岐点・・・。
すこし、そっちの方向へ歩いてみます。
ここにも横断歩道が。いずれは、ここ全域がこんな往来フリーなかんじになるんでしょうね。
写真右2枚は、奥側が相模原線の上下線。
ここの分岐も、もう使わなくなっちゃったんだなぁ。


そして、これが調布銀座の方が掛けたという横断幕。
カズナリコさんのリツイートでtokyoMXの特集を見たので、ちょっと気になって。

だいたいここの正面に昔は駅があったという事なんですが(今は全然わからない、鉄道柵は残ってます)
駅が移転してこっち側は廃れちゃったんだろうに、それでも京王線を好いててくれてるんだなぁ、
と思うとなんだかじんわりするんですが、京王は一体どれほどの洗脳を沿線民に施していr


気になったので、少し通り抜けてみました。シャッターが閉まってるお店が多いですが、
コーヒー喫茶とか、居酒屋とか、本場インド料理とかはやってて、懐かしいかんじが漂います。
途中がなぜかクランクになってました。
狭いです。が府中の裏通りよりは広いかな。
=====================================


駅の方へもどって、今度は南側にいってみました。
記念切符買うために並んだ、改札への階段も今は閉鎖されてました。

中央改札への南口の階段がわからず、そのまま東側へ。入り口がありました。



すごい。
こっちは、線路と線路の間に下へ降る階段を設けたんですね。
しかも、こっちは石造りなので本階段ぽい。
ここからの眺めも感慨深い。
ホームの下の土台って、こうなってたんだなぁ。

東口改札。
こちらは、中央改札の半分程度の規模ってかんじですね。でも穴場っぽくて使いやすそう。
「どんなかんじだった?ホームドア、あったでしょ、」と聞いたら、「あるけど、開きっぱなしだった」という返答で
「・・・・・・・・え?」
気になったので、ちょっと見てきました。昼休み使って。
マジだった。
電車が行っても、開きっぱなし。電車がきても開きっぱなし。相模原線のもおなじく。
これじゃあ、単に、とびとびで板が生えただけじゃ?
(都営車の表示が回送。これは調布止まりで、このあと引き込み線にでも待避するのかな~)
・・・しかも、なんか都心の地下で見るホームドアより、間が広いような・・・。
多少のオーバーランも大丈夫b って事なんでしょうか・・・。
運転士さんが馴れるまでは本格起動しないとか?(笑)よくわからんですが、まだまだ未完成のようです。
そして、壁の絵がむしろ怖いよ、ケイオウさん・・・。
ピンクは新宿の(京王関係の)景色かな。なにげに都庁も入れてるのは、都営への配慮?
上り線のホームから、エスカレーターをあがると下り線のホームにでました。
そこでさっそく、出口と間違えて下りのエスカレーターに乗ろうとし、止められるお年寄りの一団。
こりゃあ、しばらく混乱がおきそうだわ。
警備保障かなにかの人が、ホームにも改札にもすっごい、いっぱいいました。
中央改札口。これとは反対側に東口改札口もあるのだけど、私も一瞬混乱しました。
どっちにでても、北側南側に出られるので、別に迷うことはないんですよね。はへー
外へ出ました。中央改札からの階段は、橋上駅のときのと同じ、架設の階段でした。
途中の通路に工事中の様子や、京王線の昔の駅の写真がすこし展示されていましたが、
それがはっつけてある壁も、柔らかくて仮素材っぽい・・・。今後どうなるんでしょう、あの動線。
京王線の線路が、はやくもバッツリ切断されてて、横断歩道にされてるのに驚きました。
ここから、無人となった駅の地上ホームが見られます。
なんか、もう資材置き場と化してましたが。
相模原線の分岐点・・・。
すこし、そっちの方向へ歩いてみます。
ここにも横断歩道が。いずれは、ここ全域がこんな往来フリーなかんじになるんでしょうね。
写真右2枚は、奥側が相模原線の上下線。
ここの分岐も、もう使わなくなっちゃったんだなぁ。
そして、これが調布銀座の方が掛けたという横断幕。
カズナリコさんのリツイートでtokyoMXの特集を見たので、ちょっと気になって。
だいたいここの正面に昔は駅があったという事なんですが(今は全然わからない、鉄道柵は残ってます)
駅が移転してこっち側は廃れちゃったんだろうに、それでも京王線を好いててくれてるんだなぁ、
と思うとなんだかじんわりするんですが、京王は一体どれほどの洗脳を沿線民に施していr
気になったので、少し通り抜けてみました。シャッターが閉まってるお店が多いですが、
コーヒー喫茶とか、居酒屋とか、本場インド料理とかはやってて、懐かしいかんじが漂います。
途中がなぜかクランクになってました。
狭いです。が府中の裏通りよりは広いかな。
=====================================
駅の方へもどって、今度は南側にいってみました。
記念切符買うために並んだ、改札への階段も今は閉鎖されてました。
中央改札への南口の階段がわからず、そのまま東側へ。入り口がありました。
すごい。
こっちは、線路と線路の間に下へ降る階段を設けたんですね。
しかも、こっちは石造りなので本階段ぽい。
ここからの眺めも感慨深い。
ホームの下の土台って、こうなってたんだなぁ。
東口改札。
こちらは、中央改札の半分程度の規模ってかんじですね。でも穴場っぽくて使いやすそう。
わああーい! \(*^▽^*)/
金光さんの大正生命が、鈴木財閥破綻後「川崎財閥の傘下になってたんじゃないか?」との仮説をたててたんですが、このほど、それを立証する資料にいきあたりました。
わーーーいっ
======================================
「保険・銀行・信託早解り. 昭和9年版」大衆経済社 編/昭和9年
p266
大正生命 (東京市麹町区有楽町)
当社は大正二年四月の創立、資本金は五十万円、社長には当初柳原義光伯就任し、
専務に岡烈氏当ったが、後金光庸夫氏襲任し、鈴木系並に貿易業者を地盤として著しく好調を辿った。
然るに鈴木商店の没落からその関係を懸念され少なからぬ影響を蒙るに至り
一時川崎家の支配下に置かれてゐたが、昭和八年金光氏社長に就任して川崎の手を離れ、
専ら内容刷新に努力し今日に至っている。
当社八年度の業績を見るに、新契約は一千百四十万二千円にして、失効解約は千八百三十六万円、
結局六百二十一万四千円の契約減少を見て年末現在契約は六千四十一万五千円となったのである。
契約成績は近頃大分見直して来たとは云へ、失効解約が新契約を超過する様では問題にならぬ。
失効解約の防止に先づ努力するが肝要である。継ぎに八年度の収入保険料は二百三十一万四千円、
事業費は百四万五千円で、収入保険料百円に対して四十九円四十六銭を費ってゐる。
如何に積極的な経営とは云へこの事業費は余りに高きに失する。
もっと募集の合理化を図り、経費の節約に努めねばならぬ。
八年度末の資産は千七百七十九万二千円、諸利息収入は九十八万四千円で、平均資産利廻として高利廻と云はなければならぬ。
低金利の折柄資産利廻が前年より向上した所を見ると資産内容は七万円で内二万五千円を契約者利益配当準備金に繰入れ、株主配当は二万五千円(年五分)
を行ったが、契約者勘定に属する諸準備金は千六百九十五万七千円を算した。
△創立、大正二年四月
△現重役、社長金光庸夫、取締役田村周蔵、磯田正朝、植村俊平、監査役鈴木岩治郎
△支社所在地、東京、大阪、名古屋、仙台、京城、京都、広島、福岡、札幌、台北
△保険種類、利益配当附普通終身、祝寿養老金附終身、確定配当金附養老、生存分配金附養老、
利益配当附普通養老
======================================
やっぱり、鈴木没落後、川崎のお世話になっていたのですね。
しかも柳原義光伯が辞任したあと、「昭和八年金光氏社長に就任して川崎の手を離れ」だとう!?
ということは、昭和9年の時点で川崎と手を切っているのか!
ダンスホール事件が昭和8年の末で、金光氏社長就任の報は確か、昭和9年2月だったからな・・・。
大正生命保険会社が、川崎の支配下にあったのは昭和6~8年あたりということか。せまいがドンピシャだな!!
でも、これで長年の疑問もとけたきがする。
池上電鉄の重役も、目蒲陣営と交代する時、金光さんと後藤さんは進退を一緒にしてるんで「あれれ?」とは感じていたんですよ。
大正生命に関しては、かなり初期から京王の筆頭株主だったみたいだし、
言及されてないのが不思議なくらい。
川崎が、西武や玉川に影響を及ぼせたのも大正生命の株があったからだろうな~。
(借入金については、さすがに内部資料じゃないとわからないけど)
一応、「川崎・鴻池コンツェルン読本」(日本コンツェルン全書Ⅹ/勝田貞治著/春秋社/昭和13年)にも「(昭和)6年大正生命の経営に参与し」と、一行だけ書かれていたんですが、そこはそれだけで、川崎の影響力とか、関係の深さが不明で。
しかも、後藤さんも高梨博司さんも、川崎内の主要人物紹介から外されちゃってるんですよ!?
「川崎財閥からして、河合良成や、後藤國彦などの番頭格が出たのも、夫は、自分の名声を高めんがために、川崎財閥の意響(向?)を無視して活動し、それがために、失策を演じ、刑事事件まで、引き起こした結果ではないか。川崎財閥が何も好んで、有為の人材を追ひ出したのではない。追ひ出されたものに、その罪があるのである」
とまで、書かれて、ええ!?「追い出された」!?「刑事事件」!!?
それって、やっぱり帝人事件が、川崎内でもかなーり、立場を悪くする原因になったってことなんでしょうかね・・・。刑事事件でおもいつくのって、それしか・・・。
川崎財閥の研究本って、この昭和13年の本か、昭和5年の「日本財閥の解剖」くらいしかないんですよね。でも、ちょうど、この川崎(後藤)全盛の、昭和5年と、帝人事件後の手痛い一発喰らった後の、昭和13年という時期に、本がでてるってのは、実に・・・ラッキーというか。時勢をついてんなぁ、と。ありがたいことです。
そして、今は、利光さんと岡さんの交流関係がきになるところ。
いっても、大正生命の設立は大正2年4月で京王線の開業と同時なんですよ。
じゃあ、それ以前はどうだったのかと。
千代田瓦斯会社から探してみようと思ってるんですが、「東京ガス100年史」には、千代田ガスの経営陣にまでは言及がされてないんで、ちょっと肩すかしですね~。
そのかわり、京王プラザの冷暖房設備について、なんか書いてありました。
「ガス灯」が「電灯」と競合してて、なぜか東京電灯が、東京ガスと千代田ガスの合併について、とりもってて、電気とガスの相互関係もみていくと、色々おもしろそうです。
「千代田瓦斯払込終了」明治四十三年四月十一日(月曜日) 読売新聞
千代田瓦斯第一回払込は今十一日〆切当日なるが期日前既に払込を了せしもの多く最終日の払込は小数者に過ぎずして至極良好なれば近々創立総会を開き直に事業着手の筈なるが社長は安樂兼道氏 常務取締役は岡烈、磯部保次両氏に内定し居と云
おや?社長が利光さんじゃない。東京ガスの社史の方でも、この安樂さんになってましたが、合併時点(明治四十五年)では社長は利光さんのはず。
鈴木がどの時点から、千代田瓦斯にかかわってたのかな、とおもったら、この記事見てる限り、最初からっぽいですね。
もうちょっと、岡烈さん個人の経歴と交友関係が分かると、楽なんですがねぇ・・・。
京成の社史を読んだ時にも、初期の資金募集に参加してたらしいし。あなどれぬ。
金光さんの大正生命が、鈴木財閥破綻後「川崎財閥の傘下になってたんじゃないか?」との仮説をたててたんですが、このほど、それを立証する資料にいきあたりました。
わーーーいっ
======================================
「保険・銀行・信託早解り. 昭和9年版」大衆経済社 編/昭和9年
p266
大正生命 (東京市麹町区有楽町)
当社は大正二年四月の創立、資本金は五十万円、社長には当初柳原義光伯就任し、
専務に岡烈氏当ったが、後金光庸夫氏襲任し、鈴木系並に貿易業者を地盤として著しく好調を辿った。
然るに鈴木商店の没落からその関係を懸念され少なからぬ影響を蒙るに至り
一時川崎家の支配下に置かれてゐたが、昭和八年金光氏社長に就任して川崎の手を離れ、
専ら内容刷新に努力し今日に至っている。
当社八年度の業績を見るに、新契約は一千百四十万二千円にして、失効解約は千八百三十六万円、
結局六百二十一万四千円の契約減少を見て年末現在契約は六千四十一万五千円となったのである。
契約成績は近頃大分見直して来たとは云へ、失効解約が新契約を超過する様では問題にならぬ。
失効解約の防止に先づ努力するが肝要である。継ぎに八年度の収入保険料は二百三十一万四千円、
事業費は百四万五千円で、収入保険料百円に対して四十九円四十六銭を費ってゐる。
如何に積極的な経営とは云へこの事業費は余りに高きに失する。
もっと募集の合理化を図り、経費の節約に努めねばならぬ。
八年度末の資産は千七百七十九万二千円、諸利息収入は九十八万四千円で、平均資産利廻として高利廻と云はなければならぬ。
低金利の折柄資産利廻が前年より向上した所を見ると資産内容は七万円で内二万五千円を契約者利益配当準備金に繰入れ、株主配当は二万五千円(年五分)
を行ったが、契約者勘定に属する諸準備金は千六百九十五万七千円を算した。
△創立、大正二年四月
△現重役、社長金光庸夫、取締役田村周蔵、磯田正朝、植村俊平、監査役鈴木岩治郎
△支社所在地、東京、大阪、名古屋、仙台、京城、京都、広島、福岡、札幌、台北
△保険種類、利益配当附普通終身、祝寿養老金附終身、確定配当金附養老、生存分配金附養老、
利益配当附普通養老
======================================
やっぱり、鈴木没落後、川崎のお世話になっていたのですね。
しかも柳原義光伯が辞任したあと、「昭和八年金光氏社長に就任して川崎の手を離れ」だとう!?
ということは、昭和9年の時点で川崎と手を切っているのか!
ダンスホール事件が昭和8年の末で、金光氏社長就任の報は確か、昭和9年2月だったからな・・・。
大正生命保険会社が、川崎の支配下にあったのは昭和6~8年あたりということか。せまいがドンピシャだな!!
でも、これで長年の疑問もとけたきがする。
池上電鉄の重役も、目蒲陣営と交代する時、金光さんと後藤さんは進退を一緒にしてるんで「あれれ?」とは感じていたんですよ。
大正生命に関しては、かなり初期から京王の筆頭株主だったみたいだし、
言及されてないのが不思議なくらい。
川崎が、西武や玉川に影響を及ぼせたのも大正生命の株があったからだろうな~。
(借入金については、さすがに内部資料じゃないとわからないけど)
一応、「川崎・鴻池コンツェルン読本」(日本コンツェルン全書Ⅹ/勝田貞治著/春秋社/昭和13年)にも「(昭和)6年大正生命の経営に参与し」と、一行だけ書かれていたんですが、そこはそれだけで、川崎の影響力とか、関係の深さが不明で。
しかも、後藤さんも高梨博司さんも、川崎内の主要人物紹介から外されちゃってるんですよ!?
「川崎財閥からして、河合良成や、後藤國彦などの番頭格が出たのも、夫は、自分の名声を高めんがために、川崎財閥の意響(向?)を無視して活動し、それがために、失策を演じ、刑事事件まで、引き起こした結果ではないか。川崎財閥が何も好んで、有為の人材を追ひ出したのではない。追ひ出されたものに、その罪があるのである」
とまで、書かれて、ええ!?「追い出された」!?「刑事事件」!!?
それって、やっぱり帝人事件が、川崎内でもかなーり、立場を悪くする原因になったってことなんでしょうかね・・・。刑事事件でおもいつくのって、それしか・・・。
川崎財閥の研究本って、この昭和13年の本か、昭和5年の「日本財閥の解剖」くらいしかないんですよね。でも、ちょうど、この川崎(後藤)全盛の、昭和5年と、帝人事件後の手痛い一発喰らった後の、昭和13年という時期に、本がでてるってのは、実に・・・ラッキーというか。時勢をついてんなぁ、と。ありがたいことです。
そして、今は、利光さんと岡さんの交流関係がきになるところ。
いっても、大正生命の設立は大正2年4月で京王線の開業と同時なんですよ。
じゃあ、それ以前はどうだったのかと。
千代田瓦斯会社から探してみようと思ってるんですが、「東京ガス100年史」には、千代田ガスの経営陣にまでは言及がされてないんで、ちょっと肩すかしですね~。
そのかわり、京王プラザの冷暖房設備について、なんか書いてありました。
「ガス灯」が「電灯」と競合してて、なぜか東京電灯が、東京ガスと千代田ガスの合併について、とりもってて、電気とガスの相互関係もみていくと、色々おもしろそうです。
「千代田瓦斯払込終了」明治四十三年四月十一日(月曜日) 読売新聞
千代田瓦斯第一回払込は今十一日〆切当日なるが期日前既に払込を了せしもの多く最終日の払込は小数者に過ぎずして至極良好なれば近々創立総会を開き直に事業着手の筈なるが社長は安樂兼道氏 常務取締役は岡烈、磯部保次両氏に内定し居と云
おや?社長が利光さんじゃない。東京ガスの社史の方でも、この安樂さんになってましたが、合併時点(明治四十五年)では社長は利光さんのはず。
鈴木がどの時点から、千代田瓦斯にかかわってたのかな、とおもったら、この記事見てる限り、最初からっぽいですね。
もうちょっと、岡烈さん個人の経歴と交友関係が分かると、楽なんですがねぇ・・・。
京成の社史を読んだ時にも、初期の資金募集に参加してたらしいし。あなどれぬ。
休みなのをいいことに、日テレの朝の情報番組をえんえん垂れ流しながならキーボードうってたら、
ザ・たっちが「イセタン」と「ルミネ」とかかれた箱を胴に巻いていたので、「なんだろう」とおもって見てたら、しまいに合体して「今日からルミタン」とかいいだしたので、もうどうしたら。
伊勢丹とルミネの共同企画で「ルミタン×クリーマ」というクリエイティブマーケット?みたいのを今日からやるみたいです。
次回10月は「ルミタン×カメラ女子」で、もう、いろいろマテと。vvv
======================================
「新宿駅が二つあった頃」といっしょに借りた、
「新宿うら町おもてまち」(野村敏雄/朝日新聞社/1993年)も面白かったんで、
いろいろ抜き書きしていたんですけど、情報量が多くて、時間がかかりました。
「二つあった頃」を補完して読むのにとてもいいかんじです。前者がエッセイなら、こっちは辞書系かな。
同じオーラル系をあつかっているんだけども、扱ってる地域と年代がえらい範囲が広くて。
ビミョウに項目ごとの「筋」が飛び飛びになるので、ちょっと把握しづらいのが…、辞書っぽいなと。
著者は四代つづけての新宿住まいを自任する「新宿っ子」で、これも阿部さんとは対照的か。
しかも、自身の視点はどちらかというと従で、先人の回顧録や、地域の古老や、両親の話などをメインにおいているので、視点が定まっていないのも、対照的。
しかし、その分、情報量と精度は圧倒的。それでも、資料的には二次だから、確認のための一次資料の参照は必要かも。
======================================
以下、参考になりそうなところを要約。
○新宿駅
新宿駅の誕生は明治十八年三月。
開業当初の新宿停車場は付近に民家は一軒もなく、まわりは田畑で裏は欅の深い森だった。鉄道業務は貨物輸送がもっぱらで、旅客の利用などめったになく、汽車が着くのも一日三回。線路で蛙の大群や狐の母子が轢死していたりした。
明治も三十年代後半になって、ようやく駅前に茶店が二、三軒開店する。
乗客よりも貨物をうけとりにくる人たちのお休み処だった。
駅舎は木造で青梅街道寄りにあり、改札口は一か所で東を向いていた。
「南側は貨物の集積所で、駅構内で田中、中島の二人が売り子五、六人を使って中売りをやっていたが、父の饅頭が評判がよくて中売り商品の一つに加えられた。卸し値が一個一銭二厘で小売りは二銭となる。それを手づかみで渡し、その手で金を受け取っていた」(『豊多摩郡の内藤新宿』)
明治三十九年、鉄道は国有になり、新宿停車場の駅舎は甲州口へうつるが、鉄道業務はあいかわらずのんびりしたものだった。駅周辺が賑やかになるのは震災後である。
大正十四年に駅本屋が青梅街道口へ新築移転してから、新宿は新興の町として急カーブで発展する。
昭和にはいると駅周辺の商店街が整備され、百貨店が進出し、劇場映画館などの娯楽施設が増え、銀座をしのぐ勢いを見せる。
※このへんは「二つあった頃」でもいわれていたことですね。
ただ、明治30年代の木造駅舎は「青梅街道側」にあったとあります。
「二つ」では震災後、甲州街道側の本屋が今の位置に新築されて移ったとあるので、これはさらに、その前ということになります。本屋が青梅街道と甲州街道をいったり来たりしたということですね。
○火除けの原
火除けの原は新宿駅の南口(渋谷区代々木二丁目一帯)、小田急線の南新宿駅から甲州街道にまたがる地域で、大正大震災の前までは起伏のある広大な原っぱだった。
江戸期は「新屋敷火除御用屋敷」と称する小屋敷地と、その西が戸田山城守の抱屋敷地だった。
一部は千駄ヶ谷村の入会(いりあい・百姓地)もあったが、明治になって「字火除ケ」となり、小屋敷地跡に鉄道路線が南北に敷設された。
おふくろの時代は、子供達が火除けの原へ遊びにいくときは、みんな近道して鉄道路線を飛びこしていったという。
生前のおふくろから聞き書きをとっているとき、おふくろがいった。
「子供の時分に、冬の寒い夜なんど、狐の鳴き声がシオケの原とゴロチから、かわりばんこにきこえたもんだ。こっちでコーンて鳴くと、すぐ停車場のほうからもコーンてね。早く寝ないとおとか(稲荷=狐)様がくるよって、年寄りからいわれて、ちょっと怖かった……」
私のおふくろは家つき娘で明治三十三年の生まれである。
…おふくろの言葉に「シオケの原」とあるのは火除けの原で、「ゴロチ」は御料地(皇室御料=新宿御苑)が訛ったものである。
訛りといえば、土地の人しか知らない呼び方はほかにもある。
花園神社は「サンコイ(三光院)さん」で、淀橋浄水場は「タメ(溜)」と昔の人はいっていた。
昭和二年、小田急が開通してから火除けの原は変貌していった。
畑や草地に鉄路が走り、原の南に玩具のような千駄ヶ谷(南新宿)駅ができ、その先に山谷(参宮橋)駅ができた。一段低かった田圃の上に小田急本舎が建設され、すぐ近くに鉄道病院が生まれた。線路に沿って枕木の柵が立てられ、空き地には有刺鉄線の杭が打たれた。鉄道沿線につぎつぎと文化住宅が建ちならび、本社や鉄道病院をとりまくようにして付近には商店、医院、食べ物屋などが増えていった。
やがて練習や試合中のボールが、住宅の窓を割ったり、商店の店先へ飛びこんだり、線路の中まで転がっていくようになった。野球がやりにくくなり、チームはプレーボールがかかる前に、場所とりで神経をつかった。こうしてグラウンドを失った野球少年たちは、仕方なしに代々木の原や戸山が原まで遠出するようになった。
「シオケの原」をいう呼び名も、そしていつしか人々の口から遠くなった。
※火除け地は、「京王線・井の頭線 昭和の記憶」の冒頭の地図にも載っていました。
震災前は柵もなく子供たちが野球をする広い原っぱだったようです。
それぞれの地名が土地の言葉で呼ばれているのもおもしろい。
それが、小田急が開通して、柵ができ、遊び場も手狭になったというのも、震災後の大きな変化の一つですね。開業当初の、小田急の駅名も大分ちがいます。これは、なかなか勉強になる…。
そして、火除け地とは線路を跨いで反対側、新宿駅の南東一帯は、貨物駅として軍事上いろいろな役目を果たしたようです。
○新宿貨物駅
町の西側は広大な新宿貨物駅で、千駄ヶ谷まで敷地が延びている。
この貨物駅には日清・日露の戦争以来、事あるごとに膨大な数の兵士が送りこまれ、兵器弾薬、軍事物資が輸送集積されてきた。
貨物駅から青山練兵場まで特別軍用線路が敷設されたのは遠く日清戦争のときである。出征兵士を満載した軍用列車が貨物駅構内へ到着するたびに、町内の表(御厩=おうまや)通りは送迎の人々がおしよせて、バンザイと歓呼の声に埋まり、ついに「バンザイ横丁」の異名を生んだほどである。
いわば新宿貨物駅は戦時平時を問わず、軍事輸送の中継基地でもあったのである。
○明治通り
環状五号線の明治通りは、以前は「改正道路」と呼ばれていた。
東京市の道路計画によるとこの首都動脈の建設は、大正八年に決定し十年ごろから着工して部分的な完成を見ながら、全線開通したのは昭和九年であった。
新宿では追分から渋谷までが昭和四年、追分から大久保までが六年に完成してドッキングしている。
追分から渋谷方面へ向かう明治通りは、新宿四丁目の角から斜めに町内を貫通して千駄ヶ谷へぬけるが、ぬけたとたん左へ大きくカーブして、そこだけ不自然なくらい「く」の字形に出っぱっている。地図で見るとよくわかるが、幅員二十二メートルの大道路が、二百メートル平方の四角い町を、三角二つに分断しているのだ。
環状の流れに逆らい家並みを無視した路線といっていい。住民不在の線引きにはそれだけの理由がなければならない。家並みに沿った路線を通すと、道路は町内を出たとたん新宿御苑に突き当たり、その一部を削りとることになるからである。
明治以来、幹線道路の建設には軍事目的も重要視されてきたが、やがて満州事変が起ころうというこの時期は、いっそう軍事性は強められている。となれば一天万乗の聖域である新宿御苑を避けながら、同時に軍事輸送の中継地である新宿貨物駅に直結する路線であれば、ちっぽけな町の一つや二つどうなろうと問題ではなかったのだ。
以下は町内の古老・大久保辰雄さんからの聞き書き、
「改正道路の思い出というと、二・二六事件のときは怖ろしいという印象をうけましたね。新宿駅の貨物構内へ、宇都宮とかあっちからの連隊が全部着剣で降り立ったり、戦車もここを通りました。すごかったです。
もっとすごいのは爆撃機が通りましたよ、翼をもいで胴体だけ、深夜にね。いえ、それは二・二六のときではなくて、そのあとです。まア結局これは軍用道路としてつくったわけで、貨物駅に直行ですよね。ふつうの道路建設でしたら家並みに沿ってくるわけですが、それが貨物駅を目標ですからね、そうなんです。まして昔は何でもお国のためでしたから」
※明治通りは新宿に最初からあった道路ではなく、大正の終わりから昭和の初めにかけて造られた、新造の道路だったわけですね。それも、軍事的色彩が強く、新宿御苑を通るのは畏れ多いためか、それを避けるのに、民家などにはおかまいなしだったようです。
新宿に元からある、新宿通り(表通り・電車通り)と靖国通り(北裏通り)とはまた違った雰囲気があります。
○新宿通り
新宿駅東口から追分をへて大木戸まで、甲州街道と青梅街道を一つに重ねた古いアベニュー、新宿のメインストリート。一般に「新宿通り」と呼ばれるが、地元では「表通り」または「電車通り」といった。
新宿通りが最初に拡幅されたのは、明治二十一年の「東京市区改正」のときである。道路の北側がとりはらいになり、旧幕時代の五間半より広くなったが、まだまだ馬糞臭い宿場町に変わりはなかった。
「駅から大木戸までは町とはいうものの、江戸時代の面影もそのままに、商家も今では地方でさえも見られぬようなしょんぼりした板屋根や草葺屋根のみすぼらいい家もあり、そのうえ表通りにも空地が点在していた。一歩裏にはいれば北は大久保から早稲田辺まで藪沢あり、田圃あり、昼のなお暗き森もあって人影もない」(『豊多摩郡の内藤新宿』)
「私などの見聞でも、あの追分の交番付近には、古い大きなすすけた立場(たてば)があって、そこで馬方たちが、よく濁り酒を飲んでいた。昔の古駅のなごりがそこに漂っていて、汚物を積んだ運送車がひっきりなしに通った。そのため道のわるいこと非常なもので、秋雨の日など、まったく泥田をこねまわして歩くようなひどさだった」(白石実三『新武蔵野物語』)
立場は江戸時代に街道で人足が駕籠をとめて休息した所である。
○市電
明治三十年代になってもまだこんなものだったが、明治三十六年に市街鉄道(四谷見附~新宿追分)の開通工事が起こされ、道路がさらに拡張されて、電車がはしるようになると、新宿もいくらか新しい町に変わった。
四四会の志村富吉は、毎晩路線工事の騒音で眠れぬ夜がつづいたが、それでもいまみたいに不平なんかいう者はいなかったと「思い出の記」に書いている。
市川武夫も、表通りに初めて電車が開通するというので、太宗寺の前でいまかいまかと人垣の中で心待ちにしていたら、はるか一丁目のほうから写真で見た電車が、チンチンと運転手が足で警笛を鳴らしながら進んでくるのを見て、胸がわくわくしたと書いている。
古き良き時代がしのばれる。ちなみに電車賃は三銭均一だったという。その後、市街鉄道は東京市が買収して市営となり、「市電」と呼ばれるが、以後、昭和二十四年に路線を靖国通りへうつされるまで、新宿通りの主役でまかり通った。
昭和二十四年四月、その市電(都電)が駅前から追分までの間、軌条をすべて撤去された。
路線が靖国通りに変更され、終点が歌舞伎町にうつされたのだ。それは単なる路線変更ではなく、やがて市街地開発のお荷物として、全面廃止に向かう都電の運命の予告だったのかもしれない。
開通いらい半世紀、新宿の目ぬき通りをはしりつづけた市内電車も、ついに主役の座を追われる日をむかえたのである。
都電の軌道が撤去されたあとには、グリーンベルトなるものができた。
緑を植えこんだ中央分離帯である。
だが、それも五年後には地下鉄工事でとり壊された。地下鉄(丸ノ内線)の開通は三十四年で、同時にメトロプロムナード(新宿地下道)も竣工した。
四十一年には西口広場が完成し、もぐら道は西へも延びて四通八達した。
新宿通りの起点といっていい大ガードの拡張工事が四十三年に終わると、翌年ついに都電はすべて新宿から葬られた。
○靖国通り
以前は「北裏通り」といわれた。表通りの甲州街道と並行して、宿場の北側を東西に走る古道である。
沿道に北裏町、同飛地があり、地域を総称して「北裏」とも呼ばれた。
江戸期は武家地で表番衆町ともいった。
明治期には内藤新宿の町役場があった。当時の役場の官吏は町長以下十一人だったという。
「北裏町が通りに面する地域が長かったので、北裏通りと称していたようにおもう。ところによっては、例えば、三光院(華園神社)付近では三光院通り、番衆町辺では番衆町通りとも言っていたが、一般的には北裏通りでとおっていた」と四四会の小美濃直蔵も書いている。
「靖国通り」の呼称が生まれたのは戦後の道路交通が整備されてからだろう。
この通りは新宿駅前で青梅街道と合流し、東へいくと陸上自衛隊(旧陸軍士官学校)の前を通って市ヶ谷から九段の靖国神社に出る。むろん靖国通りの名は靖国神社からついたものだろう。
靖国神社は維新の殉難者たちを祀るため、明治天皇の意向によって明治二年に建てられている。
初め東京招魂社といったが十二年に靖国神社に改まった。それでも私の親世代までは招魂社と呼ぶ人のほうがずっと多かった。
明治の戦争でも多くの戦死者が合資されたが、日露戦争のときは、ロシアの戦利品を靖国神社へ運搬するのに北裏通りを通った。
当時は荷馬車がすれちがうくらいの狭い道だったが、新宿駅まで貨車ではこんで、
そこから荷馬車や牛車に積みかえて九段まで搬送したのだ。
私も少年期に何度も見ているが、いまおもえば、北裏通りをはこばれてきた
日露戦争の武器も、それと知らずに見ているにちがいない。
四四会の小美濃直蔵は北裏通りに近い太宗寺横丁で生まれた。彼はこう書いている。
「日露戦争で分捕った大砲を、靖国神社へ奉納するのに、この通りを運搬した。昼間は休んで、夕方から翌朝にかけて、道路に丸太を並べて枕木にして、5、6頭の牛が引っ張った。人夫の声や、枕木のきしる音で眠れない夜があった……」
運搬にコロを使い牛に曳かせたのは、大砲の従量が並外れていたからか、舗装もされてない道路だからか、途中で砂利を撒いたり古材木を敷いたりの苦労もあったらしい。
裏通りを搬路にしたのも、表(新宿)通りは市電がはしっているし、朝と午後は江戸稼ぎで混雑するしで、避けたのは当然だった。
私が見て知っている靖国通りの拡張の最初は昭和八年である。花園神社の前から大ガードの横の青バス営業所(車庫)前までが、うんと広くなった。路面も舗装されて見ちがえるほどきれいになったが、それでも表通りとは比較にならないほど自動車の往来はすくないし、人通りもぽつぽつだった。
もう一つ、北裏通りは罪人や囚人を護送する道筋だった。
北裏通りの東、牛込富久町のあたりは坂になっていて「安保坂」の名がついている。道路沿いに安保海軍中将の邸があったからである。ついでにいえば、北裏通りにはすぐ近くに大島陸軍大将の邸があり、三光町のほうには沖縄戦で自決した牛島満中将の邸があった。
歌舞伎町鬼王神社の前には若いころの東条英機が住んでいた。安保邸の裏は牛込自証院で東京監獄がその奥にある。
明治三十六年、鍛冶橋から移転した未決監だが、その隣にも監獄があった。こっちは明治八年、日本橋小伝馬町の牢屋敷がうつってきた市ヶ谷監獄で、ここでは明治十二年まで、山田浅右衛門(八代目・吉亮よしふさ)の手で斬首刑がおこなわれていた。
最後の受刑者は世に毒婦と喧伝され、妖艶の美貌をうたわれた高橋お伝、二十九歳だった。
大正七年の地図を見ると、市ヶ谷監獄はすでに町屋に変わっている。東京監獄は大正十一年に東京刑務所と改まり、昭和十二年で廃止になった。つまり、そのころまで囚人の護送はつづいたのだ。それもいまのように自動車ではない。
巡査一人に多いときは五人も六人もつながってあるいたのだ。もっとも明治末年の古老の記憶図では、一丁目にある大沢馬車屋の箇所に、市ヶ谷監獄護送用と付してある。馬車の護送もあったのである。ただし囚人馬車が使われるのは特別の場合にかぎられただろう。
囚人護送には私も小学生のとき何回も出くわしている。
粗い藁の編笠をかぶせられ、獄衣の腰と両手を前で縛られ、むき出しの脛に草履を突っかけて、猫背に項垂れて曳かれていく姿は、子供の目にも異様だった。顔が見えないのがかえって怖かった。怖いけど、かわいそうという気もした。
「編笠に会っても見てはいけない」大人たちはよくそういった。囚人とはめったにいわない。編笠という。「うン」、子供たちはうなずくが、編笠にゆきあえば絶対見ないふりをして、絶対見た。大人になって、編笠を見るなといった大人たちが少しわかるようにおもった。人間は誰でも、どこかで編笠をかぶった囚人なのである。
靖国通り地下街建設は昭和四十四年の着工である、その前年に大ガードの拡張が完工している。
戦後の復興期(二十四年)に都電の終点が駅前から靖国通りの歌舞伎町へうつされたことは前に書いた。それから三年後に西武線が高田馬場から新宿まで乗り入れて、都バスの車庫跡に西武新宿駅が開業した。
このころから歌舞伎町が急発展する。西へ西へと向かう新宿発展のやがて歌舞伎町は中心になる。
靖国通りも全面拡幅され、新宿通り明治通りよりも広くなった。
厚生年金会館やホテル本陣など大きな建物がつぎつぎに建ちならび、未完だが明治道路のバイパスが交差した。もう嘘にも裏通りとはいえない。
「編笠街道」にいたっては、古い時代物映画とおもわれてもしかたがない。
※首斬り浅右衛門については、「公家侍秘録」で有名な高瀬理恵さんが「首斬り門人帳」という漫画をだしているので、そんなオドロオドロしい、イメージはないかな。(^ ^;
「お伝」の処刑については、杉浦日向子さんが「夢幻法師」という短編でそのシーンを描いていたけど、あれが浅(朝?)右衛門の仕事の最後だったのかー。
これは「ニッポンア・ニッポン」という文庫に収録されています。
新宿通りと靖国通り、今では甲乙つけがたい交通量の道路ですが、当時でははっきり、
「表」「裏」と区別されていたのですね。「電車通り」は百貨店ができたり、日露戦争のとき、太宗寺前の通りに大きな凱旋門がつくられたほどに、華々しい道を辿っているというのに、「北裏通り」は囚人の護送や、または満州から送りこまれたロシア兵捕虜を、習志野にできた収容所へ移送する途中、新宿駅で彼らを下車させ、靖国国通りへ突き当たった歌舞伎町の原っぱで食事を与えていたら見物人で混雑したなど、エピソードも対照的です。
しかし、人通りがない分、北裏通りや明治通りは子供達の格好の遊び場だったようです。
○京王電車
大正四年五月、初めて私鉄の郊外電車が新宿へ乗り入れた。当時京王電気軌道といった京王線で、笹塚~調布間をはしっていたのが新宿まで路線延長したのだ。終点は追分交差点前の路上で、電車は一両で発着していたが、
昭和二年十月、三丁目に地上五階の京王本社ビルを建設、一階を「四谷新宿駅」とし、二階以上をターミナルデパートにして「京王パラダイス」と呼んだ。私が知っている京王電車がこれである。
そのころは二両連結で新宿高校の前を通り、南口陸橋をわたっていった。現在の西口へ始発駅をうつしたのは二十年七月である。
京王線のあと西武荻窪線(大正十一年)、小田急線(昭和二年)が開通し、市電は
新宿~月島、新宿~岩本町の二本に、角筈~万世橋を加えて三系統となり、ここに市バスや青バスの数も増えて、馬糞臭い新宿通りもようやく近代的な町並みに変わりはじめた。
だが新宿が新興都市、繁華街として急発展するのは震災後から昭和初年のことである。百貨店の進出がこの時期に目立った。三越、ほてい屋、松屋、新三越、三福、伊勢丹と新宿通りにビル建設のラッシュがつづいた。デパートの大資本は地元商店街の脅威になった。弱小資本の店舗は当然ながら客寄せや宣伝に必死になった。ふだんでも安売りの赤い幟を店頭に立て、中元大売り出しや歳末大安売りには、チンドン屋を雇ったり、散らしや景品を配ったり、福引をやったりしてデパートに対抗した。
震災後の新宿は、新興の盛り場として急発展をつづけるが、その間は火事らしい火事もなくすぎた。むろん小規模の火災やボヤくらいはあった。
昭和七年六月には、追分にある京王電車発着駅の駅ビル「京王パラダイス」(松屋デパート)の五階が火事になった。松屋デパートは東京で最初にできた(昭和三年)ターミナルデパートということもあって話題になった。
デパートといえば日本橋白木屋百貨店で、六十人もの死傷者を出した火事は、この年の十二月に起こった。歳末売り出し中の四階玩具売り場から出火し、女性員がズロースをはいていなかったため、むざむざ死んだという新聞の報道から、女性の間にズロースが普及したという話は有名だが、一時に多数の犠牲者を生んだ惨事は、新宿の松屋に影響したのだろうか。一年後に松屋デパートは閉店してしまった。
○三越百貨店
新宿に最初に進出したデパートは三越だが、いきなりいまの場所にビルが建ったのではない。関東大震災で東京が極端な物資欠乏をきたしたとき、三越では各方面に物資を供給するため、市内八ヵ所にバラック建ての分店を設けたが、その一つが新宿追分の交番ならびに「三越新宿マーケット」として十月二十八日開店した。これが新宿三越のはじまりである。
その後ほかの七店は閉鎖したが新宿店だけのこり、大正十四年十月にいまのスタジオ・アルタの所へ五階建てのビルを建設「三越食料品部」として開業した。
さらに昭和五年に現在地にあった武蔵野館の土地を買収し、ここに地上八階、地下三階の現在の三越新宿店が建てられたのである。
建坪延べ四千三百坪、従業員男六百人、女四百人という壮大さは、山の手の人々の度肝をぬいた。
当初は「新三越」と人々に呼ばれ、食料品部のほうは「二幸」と名を改めて経営した。十月十日の開店には人出と混雑が予想されたが、淀橋警察から動員された警官だけではたらずに、四谷警察の応援をうけて群衆の整理警戒にあたり、午後四時三十分には閉店した。うそかほんとか、この日の客数二十万人という。盛り場一日の人出と同数である。
○ほてい屋
三越につづいて進出したのはほてい(布袋)屋百貨店である。ほてい屋は明治二年に神奈川県の田舎で、西条氏が米屋と呉服店を開いたのがはじまりという。十二年には東京神楽坂に呉服店の店をかまえ、十五年に四谷伝馬町一丁目にうつり、呉服の老舗として繁盛したが、大正十五年三月、新宿追分の角(いまの伊勢丹)に地上六階、地下一階の百貨店を開業した。開店記念として布袋さまを染め出した鬱金木綿のお財布をお客に配ったが、私の家にもこの財布があった。
当時のほてい屋の玄関入り口に大きな布袋さまの像があったのをおぼえている。
しかし、その後のほてい屋は三越との競合に敗れて影響不振となり、当主の西条清兵衛が自殺するという悲劇をへて、昭和十年には隣接の伊勢丹に買収され、ほてい屋は新宿から消えてしまった。
○伊勢丹
伊勢丹の新宿進出は昭和八年である。伊勢丹は、明治十九年神田旅籠町に呉服屋を開業したのにはじまる。二十五年に下谷の川越屋呉服店、同二十八年に牛込の甘酒屋呉服店(市谷田町)を買収し、大呉服店の基盤を築きあげた。大震災に神田の店は灰燼に帰し、大正十三年九月新宿三丁目に仮店舗を設け、新宿進出のきっかけをつくったという。
昭和七年にほてい屋の西に隣接していた東京市電気局(市電車庫用地)が大久保新田裏へ移転して、跡地の千五十余坪が払い下げになったとき、伊勢丹では七十三万五千余円で落札し、翌八年九月、神田店をやめて、ここに地上七階地下二階の百貨店を建設し開業した。
そして同十年にほてい屋を買収した。伊勢丹の名称は屋号と創業者の名を重ね「伊勢屋丹治呉服店」だったのを、明治四十年から正式に「伊勢丹」に改めた。
百貨店の規模では三越や伊勢丹におよばないが、このほかに東京初のターミナルデパート松屋(昭和三年)が開店し、味のデパート三福(昭和七年)も追分に開業した。いわば昭和前期の新宿は百貨店ラッシュだった。
○国内初の地下街建設計画
当時(昭和六年)新宿東口から追分まで、国内最初の地下街建設が計画され、
駅を中心とする壮大な都市構想が内務省で立てられていた。その内容は、駅西口の専売局煙草工場をよそへうつし(昭和十一年東品川へ移転した)、跡地へ駅本屋を中心に小田急、京王、東横の各私鉄が乗り入れる総合駅を建設し、駅前にバス発着場と公園広場を造り、そこから地下鉄を都心へはしらせ、駅の北西部をデパート、ホテル、劇場地区にしようというものだった。が、おりから昭和恐慌の最中であり、地元商店の反対もあって計画は中断され、青写真が実現したのは、それから戦争をはさんで、三十五年を待たねばならなかった。
○専売局煙草工場
煙草工場ができたのは明治四十三年である。敷地は一万四千坪、従業員は千五百人で大半は白いエプロン姿の若い女工さんだった。この工場ができてから新宿駅が朝夕賑わうようになったという。ラッシュアワーのはしりか。
※「表通り」が宿場の街道から脱皮する過程として、市電開通→京王開通→震災後の百貨店ラッシュというのが流れとしてあるようです。
京王が「四谷新宿駅」のビルを新築したのは、この流れに感化されたものなのかはわかりませんが、三越、そして終点の向かいにほてい屋、とできていけば、「われも」となっても不思議はありませんね。京王が割と早くターミナルデパートを構えることができたのも、「新宿」だったからこそ、なのかもしれません。表通りの魔力です。
四谷新宿駅に関しては、この駅名に改名したのが昭和5年3月で、駅ビル竣工からは数年経っています。
3線4ホームだったらしく、左から乗車ホーム、降車ホーム、乗車ホーム、、降車ホームとなっていて、降りてまっすぐ行くと、左斜めに改札がならび、改札の右脇が便所、左脇が案内所と駅長室?だったようですが、降車ホームからは正面改札を通らず、地下道がのび、出口直結のようにもみえます。階上松屋へ行くには、改札を出て左にエレベーターと階段があったようです。正面改札を出て、まっすぐ行って建物を出れば表通り(新宿通り)でした。
京王の社史に、昭和7年の火事については書いてなかったと思うんですが、また隠蔽か(笑)
昭和7年て、いろいろ事件がある年だなぁ・・・。
この本の書き方だと「京王パラダイス」の中に松屋があったような印象を受けるけど、京王が「パラダイス」を開業するのは、松屋が去った後、しかたなく自社経営はじめたかんじだから、両者は両立しないんですよね。
そういえば、阿部さんの本で、伊勢丹に進出をすすめた「松屋の内藤常務」てのは、この京王松屋と銀座の松屋と、どっちの常務だったんだろう・・・。新宿の事情に詳しいのは、京王のだろうけど、伊勢丹に意見できるほどの力を持った大手は銀座のっぽいよなぁ…。
百貨店の開業年に関しては「二つあった頃」とけっこう齟齬がありますね。
これは、一次資料をちゃんとあたらないと、正解は出ないかもですね。
「二つ」のほうでは、昭和9年に、食堂デパート「三福」の前川道平社長と本多長利専務が、ほてい屋の経営に乗りこんで、廉売に次ぐ廉売の廉売商法で最後のあがきを、と書いてあり、いろいろ混戦していたみたいです。
そして、このデパート商戦でもろにあおりを食ったのは、新宿の中小商店で、これまた色々反対運動をおこし、新宿地下街の建設にも反対だったよう。
専売局跡に私鉄の総合ターミナルを、という話は、以前こちらの記事で紹介したものと同じだと思うんですが、この本だと「小田急、京王、東横」てなってるんですよね。
あれ、西武は?そして、京王も含まれたの???その場合、京王はできたばかりの四谷新宿駅のビルを棄てることになりますが・・・。ここも、ちょっとアヤシイですね。
○淀橋浄水場
淀橋浄水場ができたのはもっと早く、明治二十六年である、十万坪の武蔵野原野を切りひらいて、四つの沈澄池と二十四の濾過池をつくり、多摩川からとりいれた水を沈澄濾過して、二百万市民に供給するための施設である。起工式には来会者三千人が上野と新橋から臨時列車をしたてて、ふだんはものさびしい新宿停車場へくりこみ、主催者側は楽隊と花火で華やかに出迎えたという。
それから七十二年がすぎて浄水場は東村山へ移転した。跡地にはご存じ東京都庁が建った。
○ガスタンク
浄水場の裏には淀橋名物の巨大なガスタンクが二つあった。甲州街道の陸橋にあがるとこのガスタンクの上に富士山が見えた。ガスタンクは明治四十五年の完成で、皇居の外堀以西の市民にガスを供給した。ここは昔は梅園があったところだが、京王電車に乗ってガスタンクのそばを通ると、いつも爆発しないだろうかと、幼い頭が本気で悩んだものだ。
※ガスタンクについては、初耳です。東京瓦斯会社の物でしょうか。
追記:「京王線・井の頭線 昭和の記憶」の地図を確認した所、大正五年の地図にありました。
やはり、東京瓦斯のタンクだそうです。しかも、初めは一個なのに、昭和30年の地図で、2個にふえている・・・v
場所的には諦聴寺のすぐ近くです。新宿駅からは大部遠いなぁ。
内藤新宿では、もうないですね。新町二丁目→角筈三丁目のようです。
○西口広場
西口広場も江戸時代は松平摂津守の下屋敷で、維新後は岩倉具視の別荘・花龍園になったが、当時は摂津守からとってこの辺を「つのかみ山」と呼んでいた。
「子供たちは線路の西側にあったツノカミ山によく遊びに行きました。此処は今の西口駅前から浄水場に至る一帯で、山あり谷あり池あり鳥類もいろいろおり、狐や狸までおりました。広大な場所なので一たん迷い込むと出てくることもできないほどでしたが、子供たちは蝉やいなごをとったり、戦ごっこやかくれんぼをしました」(『新宿駅八十年のあゆみ』)
つのかみ山は明治三十年に駅構内の拡張工事でとり払われた。
現在バスターミナルになっているあたりが西口広場とよばれるようになったのは、昭和十一年までここに専売局煙草製造工場があって、それが本所横川町へ移転したあと「駅前街路予定地」となったからである。
○学校と十二社
浄水場と煙草工場のあいだには精華女学校と青物市場と工学院があった。精華女学校は明治二十二年創立というから古い。甲武線(中央線)とおなじ年である。
それよりはるかに古くて有名なのが浄水場の真裏にある十二社熊野神社である。
創建は応永年間(一三九四~一四二八)といい、中野長者の鈴木九郎が熊野の十二社を勧請したといわれるが、中野長者建立説は伝説にすぎない。ここには御手洗池と呼ばれる池や高さ四メートルの滝があり、江戸西郊の行楽地として賑わった。
『江戸名所図会』や広重の『名所江戸百景』などの画材にもなった。幕末のアメリカ領事ハリスや通訳のヒュースケンも遊びにきたという。
十二社の池も浄水場の建設で大半が埋め立てられ、一時はすっかりさびれたが、第一次世界大戦の好況で、行楽地より花柳街としてふたたび活気をとりもどした。
私の少年時代も十二社の池のまわりには、お茶屋が何軒も建ちならび、池には屋形船がうかんでいた。この池も戦後しばらくのこっていたが、やがて埋めたてられて、いまでは「池の下」というバス停の名だけがのこっている。
角筈も十二社も淀橋も以前はみな町名だったが、昭和四十六年の住居表示変更で、西口一帯はすべて西新宿に変わってしまった。…
ついでながら西口町高層ビルの第一号、京王プラザホテルが竣工したのは、皮肉なことに住居表示変更のあったその年である。
十二社については、ブラタモリですこしやっていましたね。浄水場ができたことで、廃れたのか。ナムナム~
「二つあった頃」の阿部さんの出身校もあったはず、なのだけど、ここには書いてないですね。工学院と精華女子の間にあったっぽいんですけど。
作品内でもひたすら匿名にされて、まあ、表現としてはこういう演出は全然あるほうだと思いますが、もしかして架空のものなのかなぁ・・・。
追記:ああ、これだ・・・。http://www.nihongakuen.ed.jp/about/history.html 日本学園
「日本中学 淀橋時代 大正5年(1916年)~昭和11年(1936年)」
大正5年9月校舎を新宿の淀橋に移し、同月4日から授業が再開されました。この校舎は当時の東京市外山手線の新宿駅西の比較的閑静なところでした。現在の工学院大学付近といわれています。 学校用地6,590㎡(1,997坪)。
淀橋校舎は大正12年の関東大震災には幸いにも一部破損の程度で済み、翌年の夏休に修理が行われました。
・・・まあ、こんなふうに、つきとめちゃうのも、かえって「無粋」なんですけどね・・・。orz
○関東大震災
安政二年の大地震では内藤屋敷の石垣が崩れ、四谷では上水の産め桶が壊れて水が地上に噴出し、往来がとまったと記録にあるが、大正大地震がいかに烈震だったかは、中央気象台の地震計がのこらず吹っ飛んでしまったことでも知れる。震度七・九で初動時間は十三・九秒という。震災を体験した三丁目の古老に、木造家屋は完全倒壊という状態ではないが、どの家ももうもうと土煙があがり、追分唯一の煉瓦造りの農工銀行は、無惨にも全壊したという。予期せぬところで石の脆さ、木の強さを対比され興味深かったが、この最初の揺れで、町内にあった二軒の豆腐屋から同時に火が上がった。
ちょうど昼時で揚げ物をする大鍋の油に引火したのだ。一件は田畑豆腐店、一件は籠宮豆腐店といった。
籠宮さんは戦後よそへうつったが、田畑のお婆ちゃんはいまも町内に健在である。田畑ではたまたまこのとき、いつもいる汲み取り屋さんが居合わせていて、家人と一緒に消化を手伝ってくれた。
豆腐の舟にたっぷり張ってあった水で延焼が防げたという、お婆ちゃんの話で、震災後その汲み取り屋さんにお礼がしたくてずいぶん探したが、京王沿線の農家という手がかりしかなく、とうとう探し出せなかったという。一方籠宮さんでは、不運にも鍋の日が火事につながってしまうのだ。ちなみに震災の火災原因中、油鍋は五番目にあげられている。
豆腐屋から上がった火の手は上水をこえて追分へ飛び火し、北へ這った猛火は、市電の車庫(現伊勢丹)を焼いて花園神社の手前まで灰にした。西へ延びた火勢は新宿の問屋街を火の海と化し、東へながれた火焔は太宗寺付近まで焼きつくした。焼亡五百余戸(八百とも)、羅災者三千六百八十八人を記録した。
追分では料理屋の銀世界、呉服屋の大阪屋、牛肉の長久亭、寄席の末広亭、町内では二葉保育園、山手信用組合(現大同信用金庫)、雷電神社などが焼失した。電車は路面でそのまま焼け崩れ、遊郭街では寝込みを襲われたも同然の娼妓たちが、長襦袢にしごきのまま、裸足で髪を乱しながら浜野邸の庭へ逃げこんだ。
薪炭倉庫が多い問屋街は三日三晩にわたって薪炭が燃えつづけ、さながら焦熱地獄をおもわせたという。
※「二つ」で阿部さんが「火事はまる二日、ここからも見えた。今夜もあの赤い空になるのだろうか」と、いっていたのは、新宿の薪炭屋の火事だったかもしれないですね。下町の火事も、あるにはあったんでしょうが…。
市電の車庫が燃えてますが、京王も、それなりに被害はあったようで、新宿の追分で、24号と39号が焼失、笹塚の車庫で一部が崩壊して29号が修理不能に大破、41号と48号が小破したといいます。
ほかにも、遊郭街の移転やら、夜店や縁日やら、いろいろ思い出はありますが、まずはこんなところで。
ザ・たっちが「イセタン」と「ルミネ」とかかれた箱を胴に巻いていたので、「なんだろう」とおもって見てたら、しまいに合体して「今日からルミタン」とかいいだしたので、もうどうしたら。
伊勢丹とルミネの共同企画で「ルミタン×クリーマ」というクリエイティブマーケット?みたいのを今日からやるみたいです。
次回10月は「ルミタン×カメラ女子」で、もう、いろいろマテと。vvv
======================================
「新宿駅が二つあった頃」といっしょに借りた、
「新宿うら町おもてまち」(野村敏雄/朝日新聞社/1993年)も面白かったんで、
いろいろ抜き書きしていたんですけど、情報量が多くて、時間がかかりました。
「二つあった頃」を補完して読むのにとてもいいかんじです。前者がエッセイなら、こっちは辞書系かな。
同じオーラル系をあつかっているんだけども、扱ってる地域と年代がえらい範囲が広くて。
ビミョウに項目ごとの「筋」が飛び飛びになるので、ちょっと把握しづらいのが…、辞書っぽいなと。
著者は四代つづけての新宿住まいを自任する「新宿っ子」で、これも阿部さんとは対照的か。
しかも、自身の視点はどちらかというと従で、先人の回顧録や、地域の古老や、両親の話などをメインにおいているので、視点が定まっていないのも、対照的。
しかし、その分、情報量と精度は圧倒的。それでも、資料的には二次だから、確認のための一次資料の参照は必要かも。
======================================
以下、参考になりそうなところを要約。
○新宿駅
新宿駅の誕生は明治十八年三月。
開業当初の新宿停車場は付近に民家は一軒もなく、まわりは田畑で裏は欅の深い森だった。鉄道業務は貨物輸送がもっぱらで、旅客の利用などめったになく、汽車が着くのも一日三回。線路で蛙の大群や狐の母子が轢死していたりした。
明治も三十年代後半になって、ようやく駅前に茶店が二、三軒開店する。
乗客よりも貨物をうけとりにくる人たちのお休み処だった。
駅舎は木造で青梅街道寄りにあり、改札口は一か所で東を向いていた。
「南側は貨物の集積所で、駅構内で田中、中島の二人が売り子五、六人を使って中売りをやっていたが、父の饅頭が評判がよくて中売り商品の一つに加えられた。卸し値が一個一銭二厘で小売りは二銭となる。それを手づかみで渡し、その手で金を受け取っていた」(『豊多摩郡の内藤新宿』)
明治三十九年、鉄道は国有になり、新宿停車場の駅舎は甲州口へうつるが、鉄道業務はあいかわらずのんびりしたものだった。駅周辺が賑やかになるのは震災後である。
大正十四年に駅本屋が青梅街道口へ新築移転してから、新宿は新興の町として急カーブで発展する。
昭和にはいると駅周辺の商店街が整備され、百貨店が進出し、劇場映画館などの娯楽施設が増え、銀座をしのぐ勢いを見せる。
※このへんは「二つあった頃」でもいわれていたことですね。
ただ、明治30年代の木造駅舎は「青梅街道側」にあったとあります。
「二つ」では震災後、甲州街道側の本屋が今の位置に新築されて移ったとあるので、これはさらに、その前ということになります。本屋が青梅街道と甲州街道をいったり来たりしたということですね。
○火除けの原
火除けの原は新宿駅の南口(渋谷区代々木二丁目一帯)、小田急線の南新宿駅から甲州街道にまたがる地域で、大正大震災の前までは起伏のある広大な原っぱだった。
江戸期は「新屋敷火除御用屋敷」と称する小屋敷地と、その西が戸田山城守の抱屋敷地だった。
一部は千駄ヶ谷村の入会(いりあい・百姓地)もあったが、明治になって「字火除ケ」となり、小屋敷地跡に鉄道路線が南北に敷設された。
おふくろの時代は、子供達が火除けの原へ遊びにいくときは、みんな近道して鉄道路線を飛びこしていったという。
生前のおふくろから聞き書きをとっているとき、おふくろがいった。
「子供の時分に、冬の寒い夜なんど、狐の鳴き声がシオケの原とゴロチから、かわりばんこにきこえたもんだ。こっちでコーンて鳴くと、すぐ停車場のほうからもコーンてね。早く寝ないとおとか(稲荷=狐)様がくるよって、年寄りからいわれて、ちょっと怖かった……」
私のおふくろは家つき娘で明治三十三年の生まれである。
…おふくろの言葉に「シオケの原」とあるのは火除けの原で、「ゴロチ」は御料地(皇室御料=新宿御苑)が訛ったものである。
訛りといえば、土地の人しか知らない呼び方はほかにもある。
花園神社は「サンコイ(三光院)さん」で、淀橋浄水場は「タメ(溜)」と昔の人はいっていた。
昭和二年、小田急が開通してから火除けの原は変貌していった。
畑や草地に鉄路が走り、原の南に玩具のような千駄ヶ谷(南新宿)駅ができ、その先に山谷(参宮橋)駅ができた。一段低かった田圃の上に小田急本舎が建設され、すぐ近くに鉄道病院が生まれた。線路に沿って枕木の柵が立てられ、空き地には有刺鉄線の杭が打たれた。鉄道沿線につぎつぎと文化住宅が建ちならび、本社や鉄道病院をとりまくようにして付近には商店、医院、食べ物屋などが増えていった。
やがて練習や試合中のボールが、住宅の窓を割ったり、商店の店先へ飛びこんだり、線路の中まで転がっていくようになった。野球がやりにくくなり、チームはプレーボールがかかる前に、場所とりで神経をつかった。こうしてグラウンドを失った野球少年たちは、仕方なしに代々木の原や戸山が原まで遠出するようになった。
「シオケの原」をいう呼び名も、そしていつしか人々の口から遠くなった。
※火除け地は、「京王線・井の頭線 昭和の記憶」の冒頭の地図にも載っていました。
震災前は柵もなく子供たちが野球をする広い原っぱだったようです。
それぞれの地名が土地の言葉で呼ばれているのもおもしろい。
それが、小田急が開通して、柵ができ、遊び場も手狭になったというのも、震災後の大きな変化の一つですね。開業当初の、小田急の駅名も大分ちがいます。これは、なかなか勉強になる…。
そして、火除け地とは線路を跨いで反対側、新宿駅の南東一帯は、貨物駅として軍事上いろいろな役目を果たしたようです。
○新宿貨物駅
町の西側は広大な新宿貨物駅で、千駄ヶ谷まで敷地が延びている。
この貨物駅には日清・日露の戦争以来、事あるごとに膨大な数の兵士が送りこまれ、兵器弾薬、軍事物資が輸送集積されてきた。
貨物駅から青山練兵場まで特別軍用線路が敷設されたのは遠く日清戦争のときである。出征兵士を満載した軍用列車が貨物駅構内へ到着するたびに、町内の表(御厩=おうまや)通りは送迎の人々がおしよせて、バンザイと歓呼の声に埋まり、ついに「バンザイ横丁」の異名を生んだほどである。
いわば新宿貨物駅は戦時平時を問わず、軍事輸送の中継基地でもあったのである。
○明治通り
環状五号線の明治通りは、以前は「改正道路」と呼ばれていた。
東京市の道路計画によるとこの首都動脈の建設は、大正八年に決定し十年ごろから着工して部分的な完成を見ながら、全線開通したのは昭和九年であった。
新宿では追分から渋谷までが昭和四年、追分から大久保までが六年に完成してドッキングしている。
追分から渋谷方面へ向かう明治通りは、新宿四丁目の角から斜めに町内を貫通して千駄ヶ谷へぬけるが、ぬけたとたん左へ大きくカーブして、そこだけ不自然なくらい「く」の字形に出っぱっている。地図で見るとよくわかるが、幅員二十二メートルの大道路が、二百メートル平方の四角い町を、三角二つに分断しているのだ。
環状の流れに逆らい家並みを無視した路線といっていい。住民不在の線引きにはそれだけの理由がなければならない。家並みに沿った路線を通すと、道路は町内を出たとたん新宿御苑に突き当たり、その一部を削りとることになるからである。
明治以来、幹線道路の建設には軍事目的も重要視されてきたが、やがて満州事変が起ころうというこの時期は、いっそう軍事性は強められている。となれば一天万乗の聖域である新宿御苑を避けながら、同時に軍事輸送の中継地である新宿貨物駅に直結する路線であれば、ちっぽけな町の一つや二つどうなろうと問題ではなかったのだ。
以下は町内の古老・大久保辰雄さんからの聞き書き、
「改正道路の思い出というと、二・二六事件のときは怖ろしいという印象をうけましたね。新宿駅の貨物構内へ、宇都宮とかあっちからの連隊が全部着剣で降り立ったり、戦車もここを通りました。すごかったです。
もっとすごいのは爆撃機が通りましたよ、翼をもいで胴体だけ、深夜にね。いえ、それは二・二六のときではなくて、そのあとです。まア結局これは軍用道路としてつくったわけで、貨物駅に直行ですよね。ふつうの道路建設でしたら家並みに沿ってくるわけですが、それが貨物駅を目標ですからね、そうなんです。まして昔は何でもお国のためでしたから」
※明治通りは新宿に最初からあった道路ではなく、大正の終わりから昭和の初めにかけて造られた、新造の道路だったわけですね。それも、軍事的色彩が強く、新宿御苑を通るのは畏れ多いためか、それを避けるのに、民家などにはおかまいなしだったようです。
新宿に元からある、新宿通り(表通り・電車通り)と靖国通り(北裏通り)とはまた違った雰囲気があります。
○新宿通り
新宿駅東口から追分をへて大木戸まで、甲州街道と青梅街道を一つに重ねた古いアベニュー、新宿のメインストリート。一般に「新宿通り」と呼ばれるが、地元では「表通り」または「電車通り」といった。
新宿通りが最初に拡幅されたのは、明治二十一年の「東京市区改正」のときである。道路の北側がとりはらいになり、旧幕時代の五間半より広くなったが、まだまだ馬糞臭い宿場町に変わりはなかった。
「駅から大木戸までは町とはいうものの、江戸時代の面影もそのままに、商家も今では地方でさえも見られぬようなしょんぼりした板屋根や草葺屋根のみすぼらいい家もあり、そのうえ表通りにも空地が点在していた。一歩裏にはいれば北は大久保から早稲田辺まで藪沢あり、田圃あり、昼のなお暗き森もあって人影もない」(『豊多摩郡の内藤新宿』)
「私などの見聞でも、あの追分の交番付近には、古い大きなすすけた立場(たてば)があって、そこで馬方たちが、よく濁り酒を飲んでいた。昔の古駅のなごりがそこに漂っていて、汚物を積んだ運送車がひっきりなしに通った。そのため道のわるいこと非常なもので、秋雨の日など、まったく泥田をこねまわして歩くようなひどさだった」(白石実三『新武蔵野物語』)
立場は江戸時代に街道で人足が駕籠をとめて休息した所である。
○市電
明治三十年代になってもまだこんなものだったが、明治三十六年に市街鉄道(四谷見附~新宿追分)の開通工事が起こされ、道路がさらに拡張されて、電車がはしるようになると、新宿もいくらか新しい町に変わった。
四四会の志村富吉は、毎晩路線工事の騒音で眠れぬ夜がつづいたが、それでもいまみたいに不平なんかいう者はいなかったと「思い出の記」に書いている。
市川武夫も、表通りに初めて電車が開通するというので、太宗寺の前でいまかいまかと人垣の中で心待ちにしていたら、はるか一丁目のほうから写真で見た電車が、チンチンと運転手が足で警笛を鳴らしながら進んでくるのを見て、胸がわくわくしたと書いている。
古き良き時代がしのばれる。ちなみに電車賃は三銭均一だったという。その後、市街鉄道は東京市が買収して市営となり、「市電」と呼ばれるが、以後、昭和二十四年に路線を靖国通りへうつされるまで、新宿通りの主役でまかり通った。
昭和二十四年四月、その市電(都電)が駅前から追分までの間、軌条をすべて撤去された。
路線が靖国通りに変更され、終点が歌舞伎町にうつされたのだ。それは単なる路線変更ではなく、やがて市街地開発のお荷物として、全面廃止に向かう都電の運命の予告だったのかもしれない。
開通いらい半世紀、新宿の目ぬき通りをはしりつづけた市内電車も、ついに主役の座を追われる日をむかえたのである。
都電の軌道が撤去されたあとには、グリーンベルトなるものができた。
緑を植えこんだ中央分離帯である。
だが、それも五年後には地下鉄工事でとり壊された。地下鉄(丸ノ内線)の開通は三十四年で、同時にメトロプロムナード(新宿地下道)も竣工した。
四十一年には西口広場が完成し、もぐら道は西へも延びて四通八達した。
新宿通りの起点といっていい大ガードの拡張工事が四十三年に終わると、翌年ついに都電はすべて新宿から葬られた。
○靖国通り
以前は「北裏通り」といわれた。表通りの甲州街道と並行して、宿場の北側を東西に走る古道である。
沿道に北裏町、同飛地があり、地域を総称して「北裏」とも呼ばれた。
江戸期は武家地で表番衆町ともいった。
明治期には内藤新宿の町役場があった。当時の役場の官吏は町長以下十一人だったという。
「北裏町が通りに面する地域が長かったので、北裏通りと称していたようにおもう。ところによっては、例えば、三光院(華園神社)付近では三光院通り、番衆町辺では番衆町通りとも言っていたが、一般的には北裏通りでとおっていた」と四四会の小美濃直蔵も書いている。
「靖国通り」の呼称が生まれたのは戦後の道路交通が整備されてからだろう。
この通りは新宿駅前で青梅街道と合流し、東へいくと陸上自衛隊(旧陸軍士官学校)の前を通って市ヶ谷から九段の靖国神社に出る。むろん靖国通りの名は靖国神社からついたものだろう。
靖国神社は維新の殉難者たちを祀るため、明治天皇の意向によって明治二年に建てられている。
初め東京招魂社といったが十二年に靖国神社に改まった。それでも私の親世代までは招魂社と呼ぶ人のほうがずっと多かった。
明治の戦争でも多くの戦死者が合資されたが、日露戦争のときは、ロシアの戦利品を靖国神社へ運搬するのに北裏通りを通った。
当時は荷馬車がすれちがうくらいの狭い道だったが、新宿駅まで貨車ではこんで、
そこから荷馬車や牛車に積みかえて九段まで搬送したのだ。
私も少年期に何度も見ているが、いまおもえば、北裏通りをはこばれてきた
日露戦争の武器も、それと知らずに見ているにちがいない。
四四会の小美濃直蔵は北裏通りに近い太宗寺横丁で生まれた。彼はこう書いている。
「日露戦争で分捕った大砲を、靖国神社へ奉納するのに、この通りを運搬した。昼間は休んで、夕方から翌朝にかけて、道路に丸太を並べて枕木にして、5、6頭の牛が引っ張った。人夫の声や、枕木のきしる音で眠れない夜があった……」
運搬にコロを使い牛に曳かせたのは、大砲の従量が並外れていたからか、舗装もされてない道路だからか、途中で砂利を撒いたり古材木を敷いたりの苦労もあったらしい。
裏通りを搬路にしたのも、表(新宿)通りは市電がはしっているし、朝と午後は江戸稼ぎで混雑するしで、避けたのは当然だった。
私が見て知っている靖国通りの拡張の最初は昭和八年である。花園神社の前から大ガードの横の青バス営業所(車庫)前までが、うんと広くなった。路面も舗装されて見ちがえるほどきれいになったが、それでも表通りとは比較にならないほど自動車の往来はすくないし、人通りもぽつぽつだった。
もう一つ、北裏通りは罪人や囚人を護送する道筋だった。
北裏通りの東、牛込富久町のあたりは坂になっていて「安保坂」の名がついている。道路沿いに安保海軍中将の邸があったからである。ついでにいえば、北裏通りにはすぐ近くに大島陸軍大将の邸があり、三光町のほうには沖縄戦で自決した牛島満中将の邸があった。
歌舞伎町鬼王神社の前には若いころの東条英機が住んでいた。安保邸の裏は牛込自証院で東京監獄がその奥にある。
明治三十六年、鍛冶橋から移転した未決監だが、その隣にも監獄があった。こっちは明治八年、日本橋小伝馬町の牢屋敷がうつってきた市ヶ谷監獄で、ここでは明治十二年まで、山田浅右衛門(八代目・吉亮よしふさ)の手で斬首刑がおこなわれていた。
最後の受刑者は世に毒婦と喧伝され、妖艶の美貌をうたわれた高橋お伝、二十九歳だった。
大正七年の地図を見ると、市ヶ谷監獄はすでに町屋に変わっている。東京監獄は大正十一年に東京刑務所と改まり、昭和十二年で廃止になった。つまり、そのころまで囚人の護送はつづいたのだ。それもいまのように自動車ではない。
巡査一人に多いときは五人も六人もつながってあるいたのだ。もっとも明治末年の古老の記憶図では、一丁目にある大沢馬車屋の箇所に、市ヶ谷監獄護送用と付してある。馬車の護送もあったのである。ただし囚人馬車が使われるのは特別の場合にかぎられただろう。
囚人護送には私も小学生のとき何回も出くわしている。
粗い藁の編笠をかぶせられ、獄衣の腰と両手を前で縛られ、むき出しの脛に草履を突っかけて、猫背に項垂れて曳かれていく姿は、子供の目にも異様だった。顔が見えないのがかえって怖かった。怖いけど、かわいそうという気もした。
「編笠に会っても見てはいけない」大人たちはよくそういった。囚人とはめったにいわない。編笠という。「うン」、子供たちはうなずくが、編笠にゆきあえば絶対見ないふりをして、絶対見た。大人になって、編笠を見るなといった大人たちが少しわかるようにおもった。人間は誰でも、どこかで編笠をかぶった囚人なのである。
靖国通り地下街建設は昭和四十四年の着工である、その前年に大ガードの拡張が完工している。
戦後の復興期(二十四年)に都電の終点が駅前から靖国通りの歌舞伎町へうつされたことは前に書いた。それから三年後に西武線が高田馬場から新宿まで乗り入れて、都バスの車庫跡に西武新宿駅が開業した。
このころから歌舞伎町が急発展する。西へ西へと向かう新宿発展のやがて歌舞伎町は中心になる。
靖国通りも全面拡幅され、新宿通り明治通りよりも広くなった。
厚生年金会館やホテル本陣など大きな建物がつぎつぎに建ちならび、未完だが明治道路のバイパスが交差した。もう嘘にも裏通りとはいえない。
「編笠街道」にいたっては、古い時代物映画とおもわれてもしかたがない。
※首斬り浅右衛門については、「公家侍秘録」で有名な高瀬理恵さんが「首斬り門人帳」という漫画をだしているので、そんなオドロオドロしい、イメージはないかな。(^ ^;
「お伝」の処刑については、杉浦日向子さんが「夢幻法師」という短編でそのシーンを描いていたけど、あれが浅(朝?)右衛門の仕事の最後だったのかー。
これは「ニッポンア・ニッポン」という文庫に収録されています。
新宿通りと靖国通り、今では甲乙つけがたい交通量の道路ですが、当時でははっきり、
「表」「裏」と区別されていたのですね。「電車通り」は百貨店ができたり、日露戦争のとき、太宗寺前の通りに大きな凱旋門がつくられたほどに、華々しい道を辿っているというのに、「北裏通り」は囚人の護送や、または満州から送りこまれたロシア兵捕虜を、習志野にできた収容所へ移送する途中、新宿駅で彼らを下車させ、靖国国通りへ突き当たった歌舞伎町の原っぱで食事を与えていたら見物人で混雑したなど、エピソードも対照的です。
しかし、人通りがない分、北裏通りや明治通りは子供達の格好の遊び場だったようです。
○京王電車
大正四年五月、初めて私鉄の郊外電車が新宿へ乗り入れた。当時京王電気軌道といった京王線で、笹塚~調布間をはしっていたのが新宿まで路線延長したのだ。終点は追分交差点前の路上で、電車は一両で発着していたが、
昭和二年十月、三丁目に地上五階の京王本社ビルを建設、一階を「四谷新宿駅」とし、二階以上をターミナルデパートにして「京王パラダイス」と呼んだ。私が知っている京王電車がこれである。
そのころは二両連結で新宿高校の前を通り、南口陸橋をわたっていった。現在の西口へ始発駅をうつしたのは二十年七月である。
京王線のあと西武荻窪線(大正十一年)、小田急線(昭和二年)が開通し、市電は
新宿~月島、新宿~岩本町の二本に、角筈~万世橋を加えて三系統となり、ここに市バスや青バスの数も増えて、馬糞臭い新宿通りもようやく近代的な町並みに変わりはじめた。
だが新宿が新興都市、繁華街として急発展するのは震災後から昭和初年のことである。百貨店の進出がこの時期に目立った。三越、ほてい屋、松屋、新三越、三福、伊勢丹と新宿通りにビル建設のラッシュがつづいた。デパートの大資本は地元商店街の脅威になった。弱小資本の店舗は当然ながら客寄せや宣伝に必死になった。ふだんでも安売りの赤い幟を店頭に立て、中元大売り出しや歳末大安売りには、チンドン屋を雇ったり、散らしや景品を配ったり、福引をやったりしてデパートに対抗した。
震災後の新宿は、新興の盛り場として急発展をつづけるが、その間は火事らしい火事もなくすぎた。むろん小規模の火災やボヤくらいはあった。
昭和七年六月には、追分にある京王電車発着駅の駅ビル「京王パラダイス」(松屋デパート)の五階が火事になった。松屋デパートは東京で最初にできた(昭和三年)ターミナルデパートということもあって話題になった。
デパートといえば日本橋白木屋百貨店で、六十人もの死傷者を出した火事は、この年の十二月に起こった。歳末売り出し中の四階玩具売り場から出火し、女性員がズロースをはいていなかったため、むざむざ死んだという新聞の報道から、女性の間にズロースが普及したという話は有名だが、一時に多数の犠牲者を生んだ惨事は、新宿の松屋に影響したのだろうか。一年後に松屋デパートは閉店してしまった。
○三越百貨店
新宿に最初に進出したデパートは三越だが、いきなりいまの場所にビルが建ったのではない。関東大震災で東京が極端な物資欠乏をきたしたとき、三越では各方面に物資を供給するため、市内八ヵ所にバラック建ての分店を設けたが、その一つが新宿追分の交番ならびに「三越新宿マーケット」として十月二十八日開店した。これが新宿三越のはじまりである。
その後ほかの七店は閉鎖したが新宿店だけのこり、大正十四年十月にいまのスタジオ・アルタの所へ五階建てのビルを建設「三越食料品部」として開業した。
さらに昭和五年に現在地にあった武蔵野館の土地を買収し、ここに地上八階、地下三階の現在の三越新宿店が建てられたのである。
建坪延べ四千三百坪、従業員男六百人、女四百人という壮大さは、山の手の人々の度肝をぬいた。
当初は「新三越」と人々に呼ばれ、食料品部のほうは「二幸」と名を改めて経営した。十月十日の開店には人出と混雑が予想されたが、淀橋警察から動員された警官だけではたらずに、四谷警察の応援をうけて群衆の整理警戒にあたり、午後四時三十分には閉店した。うそかほんとか、この日の客数二十万人という。盛り場一日の人出と同数である。
○ほてい屋
三越につづいて進出したのはほてい(布袋)屋百貨店である。ほてい屋は明治二年に神奈川県の田舎で、西条氏が米屋と呉服店を開いたのがはじまりという。十二年には東京神楽坂に呉服店の店をかまえ、十五年に四谷伝馬町一丁目にうつり、呉服の老舗として繁盛したが、大正十五年三月、新宿追分の角(いまの伊勢丹)に地上六階、地下一階の百貨店を開業した。開店記念として布袋さまを染め出した鬱金木綿のお財布をお客に配ったが、私の家にもこの財布があった。
当時のほてい屋の玄関入り口に大きな布袋さまの像があったのをおぼえている。
しかし、その後のほてい屋は三越との競合に敗れて影響不振となり、当主の西条清兵衛が自殺するという悲劇をへて、昭和十年には隣接の伊勢丹に買収され、ほてい屋は新宿から消えてしまった。
○伊勢丹
伊勢丹の新宿進出は昭和八年である。伊勢丹は、明治十九年神田旅籠町に呉服屋を開業したのにはじまる。二十五年に下谷の川越屋呉服店、同二十八年に牛込の甘酒屋呉服店(市谷田町)を買収し、大呉服店の基盤を築きあげた。大震災に神田の店は灰燼に帰し、大正十三年九月新宿三丁目に仮店舗を設け、新宿進出のきっかけをつくったという。
昭和七年にほてい屋の西に隣接していた東京市電気局(市電車庫用地)が大久保新田裏へ移転して、跡地の千五十余坪が払い下げになったとき、伊勢丹では七十三万五千余円で落札し、翌八年九月、神田店をやめて、ここに地上七階地下二階の百貨店を建設し開業した。
そして同十年にほてい屋を買収した。伊勢丹の名称は屋号と創業者の名を重ね「伊勢屋丹治呉服店」だったのを、明治四十年から正式に「伊勢丹」に改めた。
百貨店の規模では三越や伊勢丹におよばないが、このほかに東京初のターミナルデパート松屋(昭和三年)が開店し、味のデパート三福(昭和七年)も追分に開業した。いわば昭和前期の新宿は百貨店ラッシュだった。
○国内初の地下街建設計画
当時(昭和六年)新宿東口から追分まで、国内最初の地下街建設が計画され、
駅を中心とする壮大な都市構想が内務省で立てられていた。その内容は、駅西口の専売局煙草工場をよそへうつし(昭和十一年東品川へ移転した)、跡地へ駅本屋を中心に小田急、京王、東横の各私鉄が乗り入れる総合駅を建設し、駅前にバス発着場と公園広場を造り、そこから地下鉄を都心へはしらせ、駅の北西部をデパート、ホテル、劇場地区にしようというものだった。が、おりから昭和恐慌の最中であり、地元商店の反対もあって計画は中断され、青写真が実現したのは、それから戦争をはさんで、三十五年を待たねばならなかった。
○専売局煙草工場
煙草工場ができたのは明治四十三年である。敷地は一万四千坪、従業員は千五百人で大半は白いエプロン姿の若い女工さんだった。この工場ができてから新宿駅が朝夕賑わうようになったという。ラッシュアワーのはしりか。
※「表通り」が宿場の街道から脱皮する過程として、市電開通→京王開通→震災後の百貨店ラッシュというのが流れとしてあるようです。
京王が「四谷新宿駅」のビルを新築したのは、この流れに感化されたものなのかはわかりませんが、三越、そして終点の向かいにほてい屋、とできていけば、「われも」となっても不思議はありませんね。京王が割と早くターミナルデパートを構えることができたのも、「新宿」だったからこそ、なのかもしれません。表通りの魔力です。
四谷新宿駅に関しては、この駅名に改名したのが昭和5年3月で、駅ビル竣工からは数年経っています。
3線4ホームだったらしく、左から乗車ホーム、降車ホーム、乗車ホーム、、降車ホームとなっていて、降りてまっすぐ行くと、左斜めに改札がならび、改札の右脇が便所、左脇が案内所と駅長室?だったようですが、降車ホームからは正面改札を通らず、地下道がのび、出口直結のようにもみえます。階上松屋へ行くには、改札を出て左にエレベーターと階段があったようです。正面改札を出て、まっすぐ行って建物を出れば表通り(新宿通り)でした。
京王の社史に、昭和7年の火事については書いてなかったと思うんですが、また隠蔽か(笑)
昭和7年て、いろいろ事件がある年だなぁ・・・。
この本の書き方だと「京王パラダイス」の中に松屋があったような印象を受けるけど、京王が「パラダイス」を開業するのは、松屋が去った後、しかたなく自社経営はじめたかんじだから、両者は両立しないんですよね。
そういえば、阿部さんの本で、伊勢丹に進出をすすめた「松屋の内藤常務」てのは、この京王松屋と銀座の松屋と、どっちの常務だったんだろう・・・。新宿の事情に詳しいのは、京王のだろうけど、伊勢丹に意見できるほどの力を持った大手は銀座のっぽいよなぁ…。
百貨店の開業年に関しては「二つあった頃」とけっこう齟齬がありますね。
これは、一次資料をちゃんとあたらないと、正解は出ないかもですね。
「二つ」のほうでは、昭和9年に、食堂デパート「三福」の前川道平社長と本多長利専務が、ほてい屋の経営に乗りこんで、廉売に次ぐ廉売の廉売商法で最後のあがきを、と書いてあり、いろいろ混戦していたみたいです。
そして、このデパート商戦でもろにあおりを食ったのは、新宿の中小商店で、これまた色々反対運動をおこし、新宿地下街の建設にも反対だったよう。
専売局跡に私鉄の総合ターミナルを、という話は、以前こちらの記事で紹介したものと同じだと思うんですが、この本だと「小田急、京王、東横」てなってるんですよね。
あれ、西武は?そして、京王も含まれたの???その場合、京王はできたばかりの四谷新宿駅のビルを棄てることになりますが・・・。ここも、ちょっとアヤシイですね。
○淀橋浄水場
淀橋浄水場ができたのはもっと早く、明治二十六年である、十万坪の武蔵野原野を切りひらいて、四つの沈澄池と二十四の濾過池をつくり、多摩川からとりいれた水を沈澄濾過して、二百万市民に供給するための施設である。起工式には来会者三千人が上野と新橋から臨時列車をしたてて、ふだんはものさびしい新宿停車場へくりこみ、主催者側は楽隊と花火で華やかに出迎えたという。
それから七十二年がすぎて浄水場は東村山へ移転した。跡地にはご存じ東京都庁が建った。
○ガスタンク
浄水場の裏には淀橋名物の巨大なガスタンクが二つあった。甲州街道の陸橋にあがるとこのガスタンクの上に富士山が見えた。ガスタンクは明治四十五年の完成で、皇居の外堀以西の市民にガスを供給した。ここは昔は梅園があったところだが、京王電車に乗ってガスタンクのそばを通ると、いつも爆発しないだろうかと、幼い頭が本気で悩んだものだ。
※ガスタンクについては、初耳です。東京瓦斯会社の物でしょうか。
追記:「京王線・井の頭線 昭和の記憶」の地図を確認した所、大正五年の地図にありました。
やはり、東京瓦斯のタンクだそうです。しかも、初めは一個なのに、昭和30年の地図で、2個にふえている・・・v
場所的には諦聴寺のすぐ近くです。新宿駅からは大部遠いなぁ。
内藤新宿では、もうないですね。新町二丁目→角筈三丁目のようです。
○西口広場
西口広場も江戸時代は松平摂津守の下屋敷で、維新後は岩倉具視の別荘・花龍園になったが、当時は摂津守からとってこの辺を「つのかみ山」と呼んでいた。
「子供たちは線路の西側にあったツノカミ山によく遊びに行きました。此処は今の西口駅前から浄水場に至る一帯で、山あり谷あり池あり鳥類もいろいろおり、狐や狸までおりました。広大な場所なので一たん迷い込むと出てくることもできないほどでしたが、子供たちは蝉やいなごをとったり、戦ごっこやかくれんぼをしました」(『新宿駅八十年のあゆみ』)
つのかみ山は明治三十年に駅構内の拡張工事でとり払われた。
現在バスターミナルになっているあたりが西口広場とよばれるようになったのは、昭和十一年までここに専売局煙草製造工場があって、それが本所横川町へ移転したあと「駅前街路予定地」となったからである。
○学校と十二社
浄水場と煙草工場のあいだには精華女学校と青物市場と工学院があった。精華女学校は明治二十二年創立というから古い。甲武線(中央線)とおなじ年である。
それよりはるかに古くて有名なのが浄水場の真裏にある十二社熊野神社である。
創建は応永年間(一三九四~一四二八)といい、中野長者の鈴木九郎が熊野の十二社を勧請したといわれるが、中野長者建立説は伝説にすぎない。ここには御手洗池と呼ばれる池や高さ四メートルの滝があり、江戸西郊の行楽地として賑わった。
『江戸名所図会』や広重の『名所江戸百景』などの画材にもなった。幕末のアメリカ領事ハリスや通訳のヒュースケンも遊びにきたという。
十二社の池も浄水場の建設で大半が埋め立てられ、一時はすっかりさびれたが、第一次世界大戦の好況で、行楽地より花柳街としてふたたび活気をとりもどした。
私の少年時代も十二社の池のまわりには、お茶屋が何軒も建ちならび、池には屋形船がうかんでいた。この池も戦後しばらくのこっていたが、やがて埋めたてられて、いまでは「池の下」というバス停の名だけがのこっている。
角筈も十二社も淀橋も以前はみな町名だったが、昭和四十六年の住居表示変更で、西口一帯はすべて西新宿に変わってしまった。…
ついでながら西口町高層ビルの第一号、京王プラザホテルが竣工したのは、皮肉なことに住居表示変更のあったその年である。
十二社については、ブラタモリですこしやっていましたね。浄水場ができたことで、廃れたのか。ナムナム~
「二つあった頃」の阿部さんの出身校もあったはず、なのだけど、ここには書いてないですね。工学院と精華女子の間にあったっぽいんですけど。
作品内でもひたすら匿名にされて、まあ、表現としてはこういう演出は全然あるほうだと思いますが、もしかして架空のものなのかなぁ・・・。
追記:ああ、これだ・・・。http://www.nihongakuen.ed.jp/about/history.html 日本学園
「日本中学 淀橋時代 大正5年(1916年)~昭和11年(1936年)」
大正5年9月校舎を新宿の淀橋に移し、同月4日から授業が再開されました。この校舎は当時の東京市外山手線の新宿駅西の比較的閑静なところでした。現在の工学院大学付近といわれています。 学校用地6,590㎡(1,997坪)。
淀橋校舎は大正12年の関東大震災には幸いにも一部破損の程度で済み、翌年の夏休に修理が行われました。
・・・まあ、こんなふうに、つきとめちゃうのも、かえって「無粋」なんですけどね・・・。orz
○関東大震災
安政二年の大地震では内藤屋敷の石垣が崩れ、四谷では上水の産め桶が壊れて水が地上に噴出し、往来がとまったと記録にあるが、大正大地震がいかに烈震だったかは、中央気象台の地震計がのこらず吹っ飛んでしまったことでも知れる。震度七・九で初動時間は十三・九秒という。震災を体験した三丁目の古老に、木造家屋は完全倒壊という状態ではないが、どの家ももうもうと土煙があがり、追分唯一の煉瓦造りの農工銀行は、無惨にも全壊したという。予期せぬところで石の脆さ、木の強さを対比され興味深かったが、この最初の揺れで、町内にあった二軒の豆腐屋から同時に火が上がった。
ちょうど昼時で揚げ物をする大鍋の油に引火したのだ。一件は田畑豆腐店、一件は籠宮豆腐店といった。
籠宮さんは戦後よそへうつったが、田畑のお婆ちゃんはいまも町内に健在である。田畑ではたまたまこのとき、いつもいる汲み取り屋さんが居合わせていて、家人と一緒に消化を手伝ってくれた。
豆腐の舟にたっぷり張ってあった水で延焼が防げたという、お婆ちゃんの話で、震災後その汲み取り屋さんにお礼がしたくてずいぶん探したが、京王沿線の農家という手がかりしかなく、とうとう探し出せなかったという。一方籠宮さんでは、不運にも鍋の日が火事につながってしまうのだ。ちなみに震災の火災原因中、油鍋は五番目にあげられている。
豆腐屋から上がった火の手は上水をこえて追分へ飛び火し、北へ這った猛火は、市電の車庫(現伊勢丹)を焼いて花園神社の手前まで灰にした。西へ延びた火勢は新宿の問屋街を火の海と化し、東へながれた火焔は太宗寺付近まで焼きつくした。焼亡五百余戸(八百とも)、羅災者三千六百八十八人を記録した。
追分では料理屋の銀世界、呉服屋の大阪屋、牛肉の長久亭、寄席の末広亭、町内では二葉保育園、山手信用組合(現大同信用金庫)、雷電神社などが焼失した。電車は路面でそのまま焼け崩れ、遊郭街では寝込みを襲われたも同然の娼妓たちが、長襦袢にしごきのまま、裸足で髪を乱しながら浜野邸の庭へ逃げこんだ。
薪炭倉庫が多い問屋街は三日三晩にわたって薪炭が燃えつづけ、さながら焦熱地獄をおもわせたという。
※「二つ」で阿部さんが「火事はまる二日、ここからも見えた。今夜もあの赤い空になるのだろうか」と、いっていたのは、新宿の薪炭屋の火事だったかもしれないですね。下町の火事も、あるにはあったんでしょうが…。
市電の車庫が燃えてますが、京王も、それなりに被害はあったようで、新宿の追分で、24号と39号が焼失、笹塚の車庫で一部が崩壊して29号が修理不能に大破、41号と48号が小破したといいます。
ほかにも、遊郭街の移転やら、夜店や縁日やら、いろいろ思い出はありますが、まずはこんなところで。


