たまろぐ
テツ的あれこれ妄想牧場。(※路線≒会社の擬人化前提注意です)
最近は管理人の備忘録と化してます。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
さきたま古墳群の資料館で「古代の豪族」展が15日までだと
大宮の氷川神社の図書館でみかけたのでいってみました。
ほんとは2日か3日に行きたかったんですけど、
ベランダの避難ばしごの確認だとか、風呂のリフォームで風呂場の寸法を測るだとかで
お客さんがどんどこ来るので4日になってしまいました。TへT)<マケルモンカ!)
まあ、さきたま古墳群や途中よった神社もろもろは
そのうち別に記事にするとして、とりあえず今日乗った電車関連のをピックアップ。
行きたい場所をみつけて、電車で遠出する・・・いいね!+(最高に現実逃避行動)


初っぱな乗った京王線がまたラッピングのやつでした。
実は今日の帰りの電車も向かいがまた同じラッピング車だったんで
遭遇率たかいな!!


のったら案の定、床も壁も芝生シールでした。
あと、広告がなんだかバサラ(戦国)っぽいvvv

前見たときはヘッドマークついてなかったんですけど、
今朝は陣馬のつけてるな・・・
========================================

おおみや~
最近来ることが多い・・・。一回で用事がおわらないんだもん。 orz
マックストキがいました。
今日はここから高崎線に乗って、桶川と吹上へ行きます。
高崎線はじつはほとんど乗ったことがない。
なんとなく、北埼玉以北は苦手で・・・縁が無いというか。苦手で。(鬼門だから?)
でも高崎線の駅メロはほとんど聞いたことがない、しかもエラくかわいいメロディで、
もしかして女の子っぽい・・・のかな???

桶川でおりたら駅名標が昔のでビックリする。

むかいのは、もう融合しちゃってるし。
桶川には多気比売神社(たけひめじんじゃ)があるので、それをみて行こうかと思ったんです。
武蔵国足立郡の延喜式内小社で、創立は小野神社とおなじ3代安寧天皇の頃だというので。
しかも小野宮の碑ではえたもひのことを、「え・たけひ」と表記していたので
この「たけひ・め」はその女版か??という疑惑が浮かんだ物でして。
しかしここで痛恨のミス。
歩いていけるかな?とおもったら、道が途中で工事してるは雨は降ってくるは日が照るは
遠いはで体力と時間の殆どをこの神社参りに費やしてしまい、足がぼっこわれました。
さきたま古墳まわっている内に日もとっぷりと暮れ、後半の予定を諦めることに・・・。
おなじく武蔵国内で最古を自称する鷲宮神社が、ちょうど帰り途の
伊勢崎線鷲宮駅のそばにあるらしいので、そこも寄ろうと思っていたのに・・・。orz


吹上駅。さきたま古墳群への最寄り駅です。
こちらもまたメルヒェン~。いい風吹いてるらしいです。
改札前の工作もまた凝ってる。さすが群馬はSLが大好き。
神社の教訓を得、こんどはちゃんとバスを使うことにしました。
しかし、その最寄りのバス停からさらに1km離れた場所に古墳群(公園)があるらしく
その往復でまた足が死にました・・・。
世界遺産めざすなら交通手段をもうちょっと、どうにかして欲しい。
行田折り返し行きがまた秩父鉄道の行田市駅前までいかないので、
途中で降りてまた1km程歩きましたよ。
しかも、案内看板ないから、近くの和菓子屋さんに道を聞いたりしました。
しぬかとおもった。

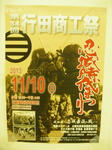
そして天国にみえた行田市駅。
ちかくに忍城という史跡があるらしい。
ポスターの武将祭がとても気になります。


あいかわらず懐かしい感じのするホーム。
自販機のラインナップもなんだか、ほっとするメニューで。
バナナココアが気になったけど、えらんだら後悔するような気がして
無難にきなこラテにしました。


15分ほど待合室でぼーっとして、電車を迎える。
なんか、やっぱりすごく叙情的だな秩鉄は。
先に来たのは三峰口行き。うっかり乗りそうになりました。


私が乗った羽生行きはこっち。
どこかで見たようなドアステッカーだったんで、東急の子かもしれない。


羽生駅ホームの反対側に急行が止まっていました。
クロスシートだ。いたんだこんな子。
羽生駅からは東武伊勢崎線に乗り換え、久喜駅まで。
そこから先は半蔵門線の車両に乗って新越谷駅で武蔵野線に乗り換えました。
東武の写真がないのは、あれです。東上線で見なれてるので目新しさがないからです←
ただ、駅ホームの赤と黒のラインカラーはすごくカッコイイと思いました。
とちゅうとちゅうで東急の車両をいっぱい見かけ、ホームには日比谷線5ドアの
ずれが気になる乗降口ステッカーを眺めながら「あーこっちは賑やかそうでいいなー」と。
半蔵門線と日比谷線は本当におなじ所で仕事してるんだねぇ・・・。
しかも東武よりはるかに東急の車両が多いってのも面白いというか。
それにしても東武本線って東武動物公園で分岐するんだ。
てっきり久喜で分岐するのかと思ってた!(なんで)


新越谷駅でみかけたポスター。
東武は紅葉で本気だしてるみたい。それ難問すぎるよ!

もひとつ気になったポスター。東武フェスタ。
これか!次、鷲宮いく機会があるとしたら!!
でも、東松山の野本将軍塚古墳も見に行きたい。
れきしスタンプも東松山駅だし。
大宮の氷川神社の図書館でみかけたのでいってみました。
ほんとは2日か3日に行きたかったんですけど、
ベランダの避難ばしごの確認だとか、風呂のリフォームで風呂場の寸法を測るだとかで
お客さんがどんどこ来るので4日になってしまいました。TへT)<マケルモンカ!)
まあ、さきたま古墳群や途中よった神社もろもろは
そのうち別に記事にするとして、とりあえず今日乗った電車関連のをピックアップ。
行きたい場所をみつけて、電車で遠出する・・・いいね!+(最高に現実逃避行動)
初っぱな乗った京王線がまたラッピングのやつでした。
実は今日の帰りの電車も向かいがまた同じラッピング車だったんで
遭遇率たかいな!!
のったら案の定、床も壁も芝生シールでした。
あと、広告がなんだかバサラ(戦国)っぽいvvv
前見たときはヘッドマークついてなかったんですけど、
今朝は陣馬のつけてるな・・・
========================================
おおみや~
最近来ることが多い・・・。一回で用事がおわらないんだもん。 orz
マックストキがいました。
今日はここから高崎線に乗って、桶川と吹上へ行きます。
高崎線はじつはほとんど乗ったことがない。
なんとなく、北埼玉以北は苦手で・・・縁が無いというか。苦手で。(鬼門だから?)
でも高崎線の駅メロはほとんど聞いたことがない、しかもエラくかわいいメロディで、
もしかして女の子っぽい・・・のかな???
桶川でおりたら駅名標が昔のでビックリする。
むかいのは、もう融合しちゃってるし。
桶川には多気比売神社(たけひめじんじゃ)があるので、それをみて行こうかと思ったんです。
武蔵国足立郡の延喜式内小社で、創立は小野神社とおなじ3代安寧天皇の頃だというので。
しかも小野宮の碑ではえたもひのことを、「え・たけひ」と表記していたので
この「たけひ・め」はその女版か??という疑惑が浮かんだ物でして。
しかしここで痛恨のミス。
歩いていけるかな?とおもったら、道が途中で工事してるは雨は降ってくるは日が照るは
遠いはで体力と時間の殆どをこの神社参りに費やしてしまい、足がぼっこわれました。
さきたま古墳まわっている内に日もとっぷりと暮れ、後半の予定を諦めることに・・・。
おなじく武蔵国内で最古を自称する鷲宮神社が、ちょうど帰り途の
伊勢崎線鷲宮駅のそばにあるらしいので、そこも寄ろうと思っていたのに・・・。orz
吹上駅。さきたま古墳群への最寄り駅です。
こちらもまたメルヒェン~。いい風吹いてるらしいです。
改札前の工作もまた凝ってる。さすが群馬はSLが大好き。
神社の教訓を得、こんどはちゃんとバスを使うことにしました。
しかし、その最寄りのバス停からさらに1km離れた場所に古墳群(公園)があるらしく
その往復でまた足が死にました・・・。
世界遺産めざすなら交通手段をもうちょっと、どうにかして欲しい。
行田折り返し行きがまた秩父鉄道の行田市駅前までいかないので、
途中で降りてまた1km程歩きましたよ。
しかも、案内看板ないから、近くの和菓子屋さんに道を聞いたりしました。
しぬかとおもった。
そして天国にみえた行田市駅。
ちかくに忍城という史跡があるらしい。
ポスターの武将祭がとても気になります。
あいかわらず懐かしい感じのするホーム。
自販機のラインナップもなんだか、ほっとするメニューで。
バナナココアが気になったけど、えらんだら後悔するような気がして
無難にきなこラテにしました。
15分ほど待合室でぼーっとして、電車を迎える。
なんか、やっぱりすごく叙情的だな秩鉄は。
先に来たのは三峰口行き。うっかり乗りそうになりました。
私が乗った羽生行きはこっち。
どこかで見たようなドアステッカーだったんで、東急の子かもしれない。
羽生駅ホームの反対側に急行が止まっていました。
クロスシートだ。いたんだこんな子。
羽生駅からは東武伊勢崎線に乗り換え、久喜駅まで。
そこから先は半蔵門線の車両に乗って新越谷駅で武蔵野線に乗り換えました。
東武の写真がないのは、あれです。東上線で見なれてるので目新しさがないからです←
ただ、駅ホームの赤と黒のラインカラーはすごくカッコイイと思いました。
とちゅうとちゅうで東急の車両をいっぱい見かけ、ホームには日比谷線5ドアの
ずれが気になる乗降口ステッカーを眺めながら「あーこっちは賑やかそうでいいなー」と。
半蔵門線と日比谷線は本当におなじ所で仕事してるんだねぇ・・・。
しかも東武よりはるかに東急の車両が多いってのも面白いというか。
それにしても東武本線って東武動物公園で分岐するんだ。
てっきり久喜で分岐するのかと思ってた!(なんで)
新越谷駅でみかけたポスター。
東武は紅葉で本気だしてるみたい。それ難問すぎるよ!
もひとつ気になったポスター。東武フェスタ。
これか!次、鷲宮いく機会があるとしたら!!
でも、東松山の野本将軍塚古墳も見に行きたい。
れきしスタンプも東松山駅だし。
PR
こんばんは。
最近、帰り途では色々と頭の中でごちゃごちゃ考えてるのに
机の前に座るとまっ白になって何も浮かばない日々が続きます。
今日は帰りにやや地味めな競馬場ラッピング車を見たので
その写真だけ。
馬関連ならラッピングするようになったなぁ・・・京王。
その前は映画の宣伝だったけど、あれは一度も行き会わなかったな。
バスもなにやら新しいギャラリー企画を?
ギャラリーバスってのはけっこう前から走ってるんですけど、
ここまででかい絵を外側につけてはいなかったな。
100周年関連でしょうか。
あ、まだれーるランドいってない。
===========================================
今日まで拍手をぽちぽちありがとうございました。
あんまり鉄道関係ないのに、すみませんです。
鉄道話題に古代を無理矢理ひきよせますと、啓文堂が5倍ポイントセール中だったんで
このあいだ塔文社からでてるレトロマップシリーズというのを買ったんですね。
これが昭和19年の鉄道路線図でして京王はまだ京王なんですけど、
その他3社が東急になってて、よくわからなかった厚木方面の混乱具合が若干判りました。
相模鉄道が厚木でわかれる中新田口行きの支線をもってて、
本線は中新田駅なんですね。
小田急の乗換駅?は河原口で、東急の事業目的のなかに
相模と神中と小田急の連絡をなんとかするってのがあったと思うんですが、
あらためて路線でみるとわりとヒドイ配置になってます。
そしてヒドい事になったのは厚木に接続駅を設けず河原口で開設した小田急のせい
ってのがウチでの解釈だったりします。
で神中が小田急と直通する為に設けたのが海老名駅で、
小田急でも海老名駅を設ける為にその手前の「海老名国分」駅というのを廃止したんですが、
この国分ってのはもしかして相模国分寺のことかな、と思いまして。
しかもよく見ると、神中のほうにも「相模国分」という駅があったのですね。
この相模国分は信号所として一応残ってらしいのですが・・・。(ウィキ)
というのを、今更になって気づきました古代ってすごいね!
お礼は、なにか更新なり絵なりを描いてから~と思ってたんですけど、
ネタがないのとリフォームや防災訓練で人の出入りが多くて
家の中が落ち着かないので原稿が拡げられなくて。すみません。
線画からデジタルできる人間だったら良かったのになぁ・・・
絵を描かなくなると平気で半年ぐらい描かなくても平気なんで
これはやばい、というか冬がもうヤバイを越えているきがする。
今日は川越の氷川会館で友人の結婚式に出席してきました。
もうここ一ヶ月はその準備で気持ちがいっぱいいっぱいでした。
なにしろ初めてのおよばれで、服とか靴とかバッグとかそういうの
全く持ってなかったんで。閉店直前の京王ファッション店街にかけこんで
マネキンさして「これください!」で決めましたからね。
まあ、なんとか滞りなく終わって良かったです。
一時は台風まで結婚する勢いでしたが、なんとか晴れましたね。
よかったよかったマジで。雨だともう、傘一本もつだけでもめんどくさい。
晴れ着をガードするなんて無理だよ。
そんなわけで、帰りは東上線です。
行きはJRで大宮まで行って、氷川神社(本家)にお参りしてから、
川越線で川越いったんで、電車もバスも本数少なくて到着はギリギリでした。
ちなみに氷川会館は川越氷川神社の付属施設です。
その記事はいつかそのうち。
そんでもって東上線ですよ、ひさしぶりの。
もう、元町・中華街までの電車がばっちりです。
でも各停なんだな・・・。これ乗るか?埼玉の人。
(副都心線内では急行になるらしいけど。逆の方がいいんじゃ?)
朝霞台で一緒に乗って来た友達とお別れし、ちょっと元町行きをまってみる事に。
うまくいったら、東急の車両と東上線の車両のツーショットとれるかも?
とドキドキしながら待つ。
したら、下りが8000形でした!まだいきてた!!/////
しかし残念なことに、上りで来たのは副都心線の車両。
まあせっかくだから、これで。
ちょっと珍しい顔の子だなと。
思ったら、LEDが大参事になってた。
京王線中河原駅から鎌倉街道を北上し、左に折れると宮前公園というのがあり、
その奥に武蔵国一宮の論社・小野宮小野神社があります。
多摩市一宮にも小野神社があり、多摩川の洪水により、この府中市の小野宮から遷座し、
水がひいて、再びこの地に戻ったのが小野宮で、多摩市に残ったのが一宮だというのが
府中市の見解です。
なので祭神は多摩市一宮とおなじ天下春命と瀬織津姫命なのですが、
ここではさらに兄多毛比命を祀っているという話です。
狛犬、子持ちなのが「子取り」で、毬持ちなのが「玉取り」で、これは東京ではよくある
わりと新し目のスタイルなんだそう。
獅子の千尋の谷とは様子がちがい、和やかな雰囲気。
境内地は洪水で一度流されてしまったためか、古樹は見当たらず
木も細っこいのしかありません。
しかし一宮の小野神社よりもすがすがしくて居心地がいい。
(あちらはごてごてしてて、若干どんよりした雰囲気だったからな・・・)
そのかわりお社の後ろに古木の株が祀られていました。
これがご神体ないしは洪水前のご神木だったのかな・・・。
小野神社のほうを向いて、小さな社がもうひとつ。
「府中の風土記」に倉稲魂命(うかのみたま)も祭祀されているとあったから、
これがそのお稲荷さんだな。
そして、この小野宮で重要なのが小野神社の由緒を篆刻した1795年建立の碑文。
三代安寧天皇の時代に使いとして兄武日(えたけひ)がやってきて
国を造り、府や廟をこの地に置いたと読めます。
=========================================
小野宮者在武藏州多麻縣小野村在昔
安寧天皇使兄武日命國造 此州兄武建府於此縣置祖廟於此地
兄武者下春大神之後 二井諸忍野神狭命九世孫
下春者天孫隨駕三十二神之一 而威靈之最也 遂稱縣曰縣府中 號廟一宮
時謂州爲國 謂守爲造 謂廟爲宮 謂創爲一皆古言也
小野元縣名府中日顯 而小野月隱 地屬多麻縣 而名僅存於村落耳
葢上古質朴無廟號 獨依地而稱矣 今也小祠存羊
亦其名見於延喜式神名帳 爲古廟也 明矣旁有枯株
周囲十尋許 其上可坐百人 瀰枝高聳摩天 殆乎有二千餘歳之想
爲故地也明矣 創降建置莫古焉 舊制威靈鍾於此 宜也四方祈福隨應有驗
内藤子章名重喬好古善醫 今茲傷其衰 修廟勒碑使余銘焉 長島侯援筆篆碑面
銘曰 鍾靈創祠 二千餘年 志士勒碑 不朽是傳 寛政七年九月望日
出雲國下大夫江都鳩谷孔平信敏撰 男信龍渉筆
次信鳳修約 長島侯人藤原巖恭書 内藤重喬肅建
=========================================
兄武日は兄多毛比の「毛」を「け」と読んだために、あてられた文字のようです。
またここでは小野神社の祭神である天下春命が、
兄武の十世代前の祖とされているように見えます。
二井諸忍野神狭命というのは「国造本紀」で
无邪志国造(むさしのくにのみやつこ)
成務朝の御世に、出雲臣の祖・二井之宇迦諸忍之神狭命の十世孫の兄多毛比命を国造に定められた。
知々夫国造(ちちぶのくにのみやつこ)
崇神朝の御世に、八意思金命の十世孫の知々夫命を国造に定められ、大神をお祀りした。
とあるのを混同したもののようです。
天下春命は八意思金命(おもいかね)の息子であり、秩父国造の祖です。
二井之宇迦諸忍之神狭命は国造本紀にしかでてこない名前ですが、
出雲臣の祖・天穂日命からわかれた分家筋の祖であり、武蔵国造の兄多毛比の先祖です。
この小野宮の碑文では
天神(八意思金と天穂日を混同)ー天下春(1)ー二井諸忍野神狭(2)ー兄多毛比(10)
と解釈し、「兄武者 下春大神之後 二井諸忍野神狭命九世孫」と書いたのでしょう。
いずれにしても、男系社会が好む「男神の系譜」であり瀬織津姫については触れていませんね。
=========================================
小野神社へ向かうとき、中河原駅の隣に建っているスーパーの根本に、なんか小さな神社があるのに気づいたんですが、「住吉町だし住吉様かな?」と思ったら、庚申様の立派な奴だった。
庚申は普通西南方向をさすので西南向きだけど、ここのは真西を向いているので
「西向庚申塔」の扁額がでっかく飾ってあります。
肝心の住吉様はどこにあるんだ、とおもったら大國魂神社の境内に
合祀されてしまっているみたいですね。
住吉銀座なのに住吉様いない・・・!(笑)
「府中のまち 紹介」(http://library.city.fuchu.tokyo.jp/about/pdf/20121228kodomohakase.pdf)
によると、中河原というのは、かつて多摩川がもっと北側(中河原と分倍河原の間くらい?)
を流路としていた頃は、浅川との間にはさまれた地域で、そのためその名前がついた
んではないか、としています。
今では浅川と多摩川の合流点はもっと上流の日野の万願寺あたりですが。
また、白糸台では繭の生産が盛んだったため、その名前がついたようで
ここで生産された繭は、世田ヶ谷の砧にもっていってさらして、
さらに八王子で織物にして国府に納めたという話でした。
そういえば、下河原緑道の入り口のインテリジェントパーク近くのマンションに
でっかい繭のオブジェがあったなぁ・・・。
タイトルは「繭のかけ橋」だそうで。
世田ヶ谷に持って行っていたということは、船の往来が盛んだったということですね。
住吉様は航海の神で海神のイメージが強いけど、海と川で区別することもないのか。
海へ行っていた神様が、船や馬に乗って川を遡って山へ帰るというのも
良くある構図だし。
ただ、小野神社に関しては、やはり多摩川南岸で祀られるのが正しいみたい。
小野神社の分布や、横山氏とのつながりなんかをみても、
瀬織津姫は多摩川南岸がテリトリーなんだな。
住吉様は北岸の、国府(中央政府)と一緒にやってきた神様ってかんじがするなぁ。
遠州にやたらと多かった、六所神社の祭神も住吉様とおなじ筒男三兄弟だし。
瀬織津姫と小野氏こと横山氏の関係も、そのうちどこかでやろうと思います。
大國魂神社の境外摂社に「坪宮(つぼのみや)」というのがあり、
それが武蔵国初代国造の兄多毛比命を祀っているということで、
場所と写真をネットで確認したら「ん?これみたことあるな???」
と思って、過去の写真をあさったら、3年前の今頃に下河原緑道を
歩いていたとき、緑道の足下にぴょろっとあった不可思議な神社だった事が判明。
せっかくだから、はんぱになってた下河原緑道の記事と一緒にあげておこう。
郷土カルタの柱がなんでここに建っていたのかも、これで納得。
府中には国造に関する伝説というか、関連設備(地名)が結構あります。
徳川の御殿地だって、国司の館があったことは証明されましたが、
もともとは国造の館があったとされる場所です。
おそらく、武蔵国のイニシアチブを握るためには、この伝説的人物
初代武蔵国造である兄多毛比命(えたもひのみこと)を祀っていることが
重要な証拠となるんです。
えたもひを祀っている神社は、ここ大國魂神社の境外摂社の坪宮の他に、
府中市住吉町の小野神社(武蔵国一の宮論社の府中側の小野神社)と
府中市若松町の人見稲荷神社(小野社から分祀したといわれる人見街道沿いの神社)と
埼玉県大宮の氷川神社(武蔵国三の宮・一の宮・総社の論社)と
埼玉県入間市の出雲祝神社(入間郡神火事件の論社の一つ)などがあります。
どれも、史料で有名な所を抑えた土地・神社です。
=========================================
エタモヒで覚えにくい場合は「武蔵のタモさん」でいいとおもいます!
(兄=えは偉大な、比=ひは彦とか姫とおなじで人をあらわすという説があり
エタモヒの本質は「タモ」にあると思われます。)
またタモは「多模=たも」という不弥国(ふみ国=北九州の宇美に否定される)の長官の
名前として中国の歴史書「魏志倭人伝」にみられ、これも官職名ではないかともいわれる。
ウィキペディアの「姓」の項には「玉・多模」として古い頃のかばねの一つに数えられています。
玉はつまり多摩、タモの名前が多摩の地名の由来とも考えられます。
やっぱり、武蔵と多摩は重複するんですねぇ。
埼玉県の由来である埼玉郡は『正倉院文書』に武蔵国前玉郡(さきたま)とあるらしく、
また上野国(群馬)に隣接して早くから発展していた児玉郡も「古玉(こだま)」
である可能性があるとすると、武蔵国における多摩はやはり埼玉県も含んだもっと
広い範囲であった可能性があります。
考古学でも3~4世紀に盛んであった南多摩の多摩川中流域の古墳群は
5世紀にはなりをひそめ、5~6世紀には埼玉の東松山や行田など北武蔵で
巨大古墳が作られる傾向がわかっていて、よく「武蔵国造の乱」として
安閑天皇紀に記された笠原直(かさはらのあたい)使主(おみ)と弟・小杵(おき)の
国造職争いに絡めて語られたりしています。
府中に国府が置かれるより以前は、たしかに埼玉方面の方が勢力優勢だったよう。
ただ、これらの南武蔵の多摩川中流域や、北武蔵の古墳群の埋葬主体が、
ただちに兄多毛比命の直系や後裔とはいえないようで、
そこにはかなりの系譜の混乱や、僭称(せんしょう)があるとみた方がいいでしょう。
=========================================
兄多毛比は主に「国造本紀」という全国の国造の系譜を記した書の、
武蔵国(无邪志・胸刺)の項に名前があるので有名です。
「国造本紀」は「先代旧事本紀(せんだいくじほんぎ)」という古文書(?)の
中に納められた数ある本紀のうちの最後の本紀です。
「先代旧事本紀」自体は徒然草で有名な吉田兼好(卜部兼好)の出身家
であり吉田神社の神職であった卜部家(吉田家)が「古事記」や「日本書紀」並に
重要な書物として大切に伝えてきた物で、中世から近世にかけては神道で絶大な人気のあった
書物なのですが、江戸後期に疑義が呈され、序文に聖徳太子と蘇我馬子が選したとあるのが
本文の内容と合わない上に、記紀(古事記と日本書紀)からの剽窃(切り貼りした引用文)が
目立つということで、後世の「偽書」と断定され、一時期学会から排除されていた書物です。
ただ、「国造本紀」は国造研究には、もうこれしか残っていないという唯一の手がかりなので
活用したいという研究者も多く、近年では「原書は失われてしまったが、元と成った書があり
「国造本紀」も序文を除けば、完全に偽書だとすること、あたわない」という考え方で
論文に取り入れられることも多くなったみたいです。
その辺の詳しい経緯については「奇書『先代旧事本紀』の謎をさぐる」(批評社)がわかりやすい。
私も論文で「新撰姓氏録」や「三代実録」は参照したんですけど、
「先代旧事本紀」は「引用するなら、きちんと気をつけなさいよ?」と教授にいわれて
真偽をいちいち確認するのも時間がないし面倒だったんで、使わなかった本なのですが、
今頃になって読む破目になるとはなぁ・・・。
(個人的には「新撰姓氏録」のほうがケアレスミスな部分が多くてイラっとする史料でした。)
神社の由緒なんかは日本書紀や古事記や先代旧事本紀を拠り所に編まれたものが多いみたいです。
で、肝心の国造とはなんぞや?というのを、このところ専門書を探して読んでみたりもしたんですけど、学会でも意見が分かれているのか、いろんなタイプがあって、掴みきれませんでした。
最初は、「国司制度になる前が国造制度なんだろう」と単純に考えていたんですけど、
国司が派遣されるようになってからでも、国造は家となったり名誉職となったりして
一応残っていたんだそうで、案外簡単に「交代!廃止!」というものでもないよう。
大宝律令で国司が派遣されるように制度が整うので、それ以前と以後の国造を学会では
「旧国造」「新国造」とか、「律令国造」とかいって区別しているようなんですが。
人によっては代々国造を勤めて居た家が、そのまま国造家を名乗り、それが滅んでからは、
一種の称号として、功績のあった貴族や武将に与えたとする説を唱えたりもして。
「うおおおおお!追い切れんわ!ダァホ!!!(@Д@;」
とりあえず、律令以後、1郡司になった国造家とか、2なれなかった国造家とか、
3国造家じゃないけど地元で力を持ってた郡司家とかがあるっぽい。
また、郡も大宝律令以前は「評(ひょう・こほり)」と言っていたことが藤原京木簡から
判明しており、郡司は評督といっていたらしいのだが、史料では「評造」という言葉があって
それの定義もあんまりわかっていない。1かもしれないし3かもしれない。
さらに中央で天皇の側近の貴族は伴造(とものみやっこ)というらしい。
律令以前の小さなクニ単位の地元有力者で中央に服属し認定されたのが「国造」であり
それ以前は県主(あがたぬし)とか稲置(いなぎ)とか小さな役職(地方官職)が
あったらしいんだけど、それはさらによく分かってない。まあ、そんなかんじ!
========================================
下河原線跡を歩こう編
スタートはインテリジェントパークから。
なんでか知らないけど、そういう名前なんです。インテリ・・・
地下を走っていた武蔵野線が顔を出すポイントでもあります。
なぜか橋の上なのに時刻表もありという、鉄にも優しい???場所です。
下河原緑道のはじまり。
路肩の側溝にちょいちょい杭が残ってるのが気になります。
別の側道と合流するあたりがちょっとした公園というか、
休憩場所みたいになっています。
それらしく駅名標とレール跡も残してあります。
レールは数十メートルで一旦とぎれ、その先は京王線と交差しています。
開業は下河原線の方が先だったから、
玉南鉄道も開業当初から土盛りで立体交差にしたと思うんですよね。
前にも載せたけど、大正13年の府中街道の交差地点ですでに土盛りの立体だったから(右)。
府中駅は地上駅だから、そこを出てから段々と勾配がついてそのまま府中街道と下河原線を
のっこしたんじゃないかなぁ。
南武線が開業する前なので(工事計画が同時期なので打ち合わせはしただろうけど)
それ以降はまた地上を走ったんだと思う。
分倍河原駅はもうちょっと北側にあったのかな?
南武線が開業したときに南武の駅へ寄せてきたという話も聞くし、
開業当初のルートは若干謎のままだなぁ・・・。
京王線を越え再び南下。
道々に地図や看板がちょいちょいあります。
また線路跡が部分だけ。
ここはこれだけです。
道路に面して左を向くと
かつての番場宿の名残をおもわせる料亭。
しかし「ラ・バンバ」というはじけたネーミングはどうしたものか・・・。
鹿島坂の説明碑。
大國魂神社の大祭の時に坪の宮に御輿が出発したことを坪の宮に報告する「
国造代奉幣式」という儀式とゆかりの深い坂だそうです。
大宝律令で国造に代わり中央から派遣されてくる官人の国司が
国の神を奉祀するようになることから「国造代」なんでしょうけども。
坪の宮は崖線下にあるので坂を下るんでしょうなぁ。
社家の鹿島田家ができたのは、おそらく鎌倉時代。
鎌倉幕府が成立してから祭祀の主体は国司から宮司や社家にうつりますんで。
旧鎌倉散歩の街道案内版になかなかいい写真が。だいぶ摩耗してますけども。
下河原線は単線なので、よく蒸気機関車がバックしながら走ってたというんですけど、
頭は常に国分寺駅方面を向いていたということかな?
次が南武線との交差地点。
南武線は府中崖線の下を通っているので、崖下に線路があり、
ここは崖の終わり目でもあります。
なので、後から開業した南武線の方が下を通り、下河原線はオーバークロスしています。
橋の上から分倍河原方面の南武線をみる。
右側の茂みは高安寺です。
南武線の昭和初期の写真をみると、この高安寺の下を通っているのがけっこう残っています。
高安寺は武蔵国安国寺であるといわれ、国分寺にならって足利政権時代に
1国1寺1塔として設立された全国の安国寺のひとつです。
しかし、平将門を倒した藤原秀郷(俵藤太)とも縁が深いとか、
源義経が立ち寄ったときに弁慶が使った井戸があるとか、伝説には事欠かないお寺です。
一番右の写真は、橋の上から府中本町駅方面を望んだもの。
この頃って駅前のイトーヨーカドーが撤退した時期だったんだなぁ。
セブンマークの看板が覆い隠されてて、みょうに寂しい気分だった。
今はラウンドワンになって、ボーリングピンがすごい光ってます。
そして、南武線もこえて、しばらく歩くと、今度は左側の足下に気になる茂みと
社の背中が目に入ったので、道を外れて正面に廻ってみると、
先ほどの坪の宮(冒頭の写真参照)だったのです。
この時は、「なんだか随分こじんまりとした社が変な位置に残っているな???」と
気になったものの、そのままにして調べませんでしたが、まさかそんなに重要なお社とは。
ということは、ですよ?
下河原線が現役の頃は、この坪宮の後ろを、蒸気機関車や貨車がガンガン走っていた、
と、こういう面白い景色が見られた訳ですね?
いやー、そんな当寺の写真が残ってるのなら、みてみたいわー。
今では、とても閑静な場所になってよかったですね・・・?
再び緑道にもどって、あとはひたすらゴールまで歩きます。
この辺になると、もうめぼしい遺蹟もなくてですね。
競馬場へ向かう路線の分岐点が残っている位です。↑
かわりに、華やかな植物がわわ~!っとサイドを飾って居る。
こころひそかに「花葬」を連想したものです。
中央自動車道を越えた辺りで、農地と工場地帯に入っていきます。
サントリーの工場があるせいか、左側がビール瓶ケースの山。
そして右側がいまがさかりのコスモス畑でとても綺麗です。
更に進むと、今度は化学工場があるらしく、ツンとした刺激臭が漂います。
反対側は収穫後の稲田です。
ふたたび緑のトンネルっぽい隔絶された道に戻りました。
周囲は住宅街なのか、あまり動きもありません。
道端にあったベンチが、ちょっと野外向きでないかんじなので
「これも駅の備品かなぁ?」と思いました。
終点に近づき、道が大きくカーブします。
多摩川の河川敷が近いのか、砂利採集の跡地なのか。
開けた場所に気になる施設とテトラポッド。
ゴールはなんの変哲もない、ちいさな公園です。
これといった記念物があるわけでもなく、とても静かなフェードアウトっぷりです。
公園はこの交差点で切れますが、道(緑道ではない)はまだまだつづきます。
下河原の土地を説明する碑がありました。
下河原は昔は対岸の連光寺に属していたんですね。
連光寺とか、市外の人はほとんど知らないローカルな地名だと思うんですけど、
歴史はけっこうありそうな感じですね。
先ほどの交差点の道を、道になりにすすむと、いくばくも歩かないうちに
実は京王線の中河原駅に着きます。
つまり、下河原線の終点と、玉南の中河原駅は案外近いということです。
このへん、話し相手ができたってことで、個人的にはうはうはなポイントです。
撮影日から随分間が空きましたが、今時分がちょうど同じ景色だとおもうので
機会がありましたら是非。


